 |
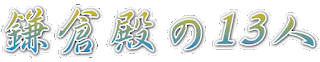
(2022/12/19更新)
|
|

The 13 Lords of the Shogun
| 2022年の大河ドラマは『鎌倉殿の13人』(かまくらどのの13にん)。 北条義時が鎌倉幕府の権力者となるまでを描いたドラマになるそうです。 |

12月18日 完
| 2023年の大河は、『吾妻鏡』を愛読し、源頼朝を尊敬していたという徳川家康。 |
| 2021年の鶴岡八幡宮の「ぼんぼりうちわ」は、「鎌倉殿の13人」の脚本を手掛ける三谷幸喜先生の揮毫。 |
| 2022年は、小栗旬さん・大泉洋さんなど出演者の皆さんの雪洞が掲揚されました。 |
大河ドラマ館の設置場所
韮山時代劇場 (伊豆の国市) |
(鎌倉市) |
| 北条義時生誕の地は「韮山時代劇場」で1月15日オープン! 鎌倉は、鶴岡八幡宮境内にある「鶴岡ミュージアム」で3月1日オープン! |

公開された頼朝像と厨子
| 11月23日(水・祝)、伊豆の国大河ドラマ館が設置されている韮山時代劇場で、島田市の智満寺に聳えていた源頼朝お手植えの頼朝杉で造立された「源頼朝像」が公開されました。 |
| 「鎌倉殿」とは? |
| 「鎌倉殿」(かまくらどの)は、鎌倉武家政権の長。 1180年(治承4年)8月17日、伊豆国で源氏再興の挙兵をした源頼朝。 10月6日(7日とも)には源氏ゆかりの鎌倉に入って本拠とし、12月12日には新造の御所で御家人311人から「鎌倉の主」に推戴されました。 |
〜鎌倉殿と征夷大将軍〜
| 「鎌倉殿」=「征夷大将軍」であったとは限りません。 1180年(治承4年)、源頼朝は関東を制圧して鎌倉殿と呼ばれるようになりますが、征夷大将軍になったのは1192年(建久3年)のこと。 二代源頼家は、1199年(建久10年)1月に家督を相続しますが、征夷大将軍になったのは1202年(建仁2年)7月のこと。 1219年(建保7年)1月、三代源実朝が暗殺された後は、九条頼経が鎌倉殿として迎えられますが・・・ 頼経が幼かったことから北条政子が後見人となり、尼将軍と呼ばれるようになります。 以後、『吾妻鏡』では政子を鎌倉殿として扱っているようです。 |
〜鎌倉殿〜

| 源頼朝は、河内源氏の棟梁源義朝の子。 母は由良御前。 1159年(平治元年)の平治の乱後、伊豆国の蛭ヶ小島に流されていましたが、1180年(治承4年)に挙兵。 鎌倉を本拠として武家の都を築き上げました。 |

| 源頼家は、頼朝の次男(北条政子の長男)。 頼朝亡き後、家督を継ぎますが・・・ 乳母夫の比企能員と外祖父の北条時政の争いに巻き込まれ、伊豆の修禅寺に幽閉された後、暗殺されました。 |

| 源実朝は、頼朝の四男(北条政子の次男)。 兄頼家の失脚後、家督を継ぎ、後鳥羽上皇とも良好な関係を築いていましたが、鶴岡八幡宮での右大臣拝賀式後に甥の公暁に暗殺されました。 |
| 「13人」とは? |
| 「13人」とは、源頼朝に仕えた有力者たちのうち、頼朝亡き後、二代頼家の時代に執られた政策「十三人の合議制」の構成員。 |
〜宿老13人の合議制〜
| 『吾妻鏡』によると・・・ 1199年(建久10年)1月13日、鎌倉に武家の都を創った源頼朝が死去すると、嫡男の頼家は20日に左中将となり、26日には頼朝の家督を相続します。 しかし・・・ 頼家の政治手腕に不安を抱いた宿老たちは、4月12日、頼家が直接訴訟を裁断することを停止させ、宿老十三人による合議によって裁判することを決定しています。 ただ、上記の理由は『吾妻鏡』から推測できるものであって、どのような理由から親裁停止としたのかは議論があるようです。 また、親裁停止ではなく、訴訟制度を整備したもので、「頼家への取次者13人が決定された」という説があります。 さらに、頼朝亡き後、幕府の主導権を握ったのは、大江広元・中原親能ら貴族出身の官僚であったことから、有力御家人の不満があったという説も。 |

(参考)
| 頼朝の死の直後に起きた三左衛門事件を鎮静させたのは、大江広元と中原親能だった。 |
| |
(参考)
| 1200年(正治2年)5月の陸奥国の境界裁定は、三善康信の取次によって頼家が裁決したものだった。 |
| 合議制の構成員13人 |
| 合議制の構成員のうち、4人は京都出身の官僚。 8人は経験豊かな御家人。 そして、もう一人は当時38歳だったという若い北条義時。 源頼朝の時代は完全な独裁政治。 頼朝は武家の棟梁として東国の武士団(御家人)との主従関係を維持する一方で、公家を側近(官僚)として採用します。 官僚は、次第に地位が高められて大きな権限を持つようになりますが、頼朝の時代は、その独裁によって御家人と官僚との調和が保たれていたようです。 しかし、頼朝が亡くなると、そうはいきません。 有力御家人と官僚の双方が納得する決着点が「13人の合議制」だったという説があります。 また、若い北条義時が構成員に名を連ねた背景には、父の北条時政と姉の北条政子の存在が大きいのかと思われますが、時政と義時は他の御家人とは異なり、官僚に近い立場にあったという説もあります。 |

| 北条時政は、伊豆国田方郡北条を拠点とした在地豪族で源頼朝の挙兵を援助しました。 頼朝亡き後、梶原景時・比企能員・畠山重忠を滅ぼしますが、後妻の牧の方とともに謀反を企てて伊豆国に追放され、北条の地で亡くなりました。 |

| 北条義時は、北条時政の次男。 頼朝に信頼されて側近として活躍し、父時政の失脚後は執権として幕政に関わりました。 和田義盛を滅ぼし、後鳥羽上皇が起こした承久の乱を鎮圧しています。 |

| 大江広元は、頼朝に招かれて鎌倉に下向してきた公家。 公文所・政治の別当を務めました。 |
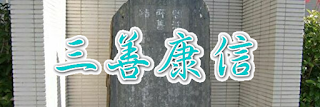
| 三善康信の母は頼朝の乳母の妹。 頼朝に誘われて鎌倉に下向し、問注所の執事を務めました。 |

| 中原親能は、幕府の草創期に頼朝に招かれて下向した公家出身の御家人。 大江広元の兄。 妻の亀谷禅尼は、頼朝の次女三幡の乳母を務めています。 |

| 三浦義澄は、頼朝の挙兵時に命を落とした三浦義明の次男。 鶴岡八幡宮で行われた頼朝の征夷大将軍の辞令交付では、義澄が辞令を受け取りました。 |

| 八田知家は、下野国宇都宮氏の二代当主・宇都宮宗綱(八田宗綱)の四男。 頼朝の乳母寒河尼の兄弟。 |

| 和田義盛は、杉本義宗(三浦義明の長男)の子。 侍所の別当を務めましたが、頼朝亡き後、北条義時に滅ぼされました。 |

| 比企能員は、頼朝の乳母比企尼の猶子(甥)。 源頼家の乳母夫となり、娘の若狭局が頼家の側室となって一幡を産んだことから権勢を強めますが、北条時政に暗殺されました。 |

| 安達盛長は、頼朝が伊豆国の蛭ヶ小島の流人だった頃からの側近。 妻は、比企尼の長女・丹後内侍。 |

| 足立遠元は、武蔵国足立郡を本拠とした豪族。 |
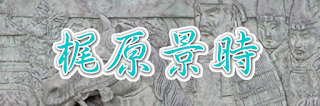
| 梶原景時は、石橋山の戦いで平家方にありながら頼朝を助けたという武将。 頼朝亡き後、結城朝光を讒言したとして鎌倉を追放され、駿河国清見関で討死しました。 |

| 二階堂行政の母は頼朝の母由良御前の従姉妹。 |

| 北条政子をはじめとする北条一族や頼朝に仕えた武将など。 |

| 知られざる義時・頼朝をご紹介。 |

| 義時が生きた時代に起きた合戦・謀反・暗殺の歴史。 |

| 伊豆・鎌倉・京都などで義時ゆかりの地・・・。 |

| 伊豆・鎌倉・奈良・京都・大阪・平泉など。 |

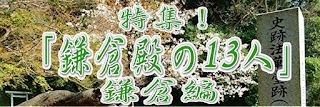




 |
 |
 |
 |
|
|