 |
 |
 |
 |
��13�q���莎���R��
�s���j�E���Ղ̖��t
|
|
| �@���q�̗��j�E���ՂɊւ���L�q�ɂ��āC�ł��K���Ȃ��̂� 1 �` 4 ����I�тȂ����B |
| �i�P�j | ���q�s�͍��N�s�������N���}���邩�B |
| �P�@60���N �R�@100���N |
�Q�@80���N �S�@120���N |
| �@�s���ɂ��Ă̖��́A��1�q�����A��3�q�����ɏo�肳��܂����B �@��3��̂Ƃ���70���N�B �@���q�s�͂P�X�R�X�N�i���a�P�S�N�j�ɁA���q���ƍ��z�����������Ďs�ƂȂ�܂����B |
���@�Q
| �i�Q�j | ���厛�ċ��̊��i�̂��߁C���s�������ɕ����r���C���q�ʼny��������b���c��l���͂��ꂩ�B |
| �P�@������ �R�@������ |
�Q�@������ �S�@�k�𐭎q |
| �@���s�́w�R�ƏW�x��҂��ƂŒm���Ă���̐l�B �@�̐l�Ƃ��������������ȂƎv���������邩������܂��E�E�E �@�w��ȋ��x�ɂ��ƁE�E�E �@�P�P�W�U�N�i�����Q�N�j�W���P�T���A���厛�ċ��̊��i�̂������B�������r���̐��s�����q�ɗ������܂��B �@�������́A�߉������{�̒����t�߂�p�j���Ă������s���B �@�䏊�ɏ����Ęa�̂�|�n�̂��Ƃɂ��Đq�˂��̂��Ƃ����܂��B |
���@�Q

| �i�R�j | 2 �㏫�R�̊O�ʂƂȂ�C���͂�U��������C�k���������̊�Ă��k�𐭎q�ɒm���C���z�̖k�������@�Ŗd�E���ꂽ�Ɠ`���l���͂��ꂩ�B |
| �P�@��t��� �R�@�����i�� |
�Q�@�O�Y�`�� �S�@���\�� |
| �@�P�Q�O�R�N�i���m�R�N�j�V���A����������ď�ԂƂȂ������Ƃ���n�܂����k�������̖d���B �@�X���Q���A���Ƃ́A���\���ɖk�������̋���^���܂����E�E�E �@�����A�����́A�\�������@�i���z���j�ɗU���o���A�V�쉓�i���m�c�����ɖ����ĈÎE���܂����B�@ |
���@�S

| �i�S�j | �ŏ��̐ۉƏ��R�Ƃ��āC�킸�� 2 �Ŋ��q���{�� 4 �㏫�R�Ɍ}����ꂽ�l���͂��ꂩ�B |
| �P�@�����i����j���� �Q�@�����i����j���o �R�@�����i����j���k �S�@�����i����j�njo |
| �@�P�Q�P�X�N�i���ۂV�N�j�A�O�㏫�R���������ÎE�����ƁA�k�𐭎q�͐e�������R�Ɍ}���悤�Ƃ��܂����A�㒹�H��c�ɋ��ۂ��ꂽ���߁A��Ƃ̎O�j�E�O�Ёi�̂��̗��o�j���}�����܂����i�ۉƏ��R�j�B �@���o�́A�������̎o�i���j�V��P�̑\���B �@�c���O�Ђ̌㌩���͐��q�B �@���̎�����A���q�͓R�ƌĂ�܂��B |
���@�Q

| �@���v�̗��́A�������̈ÎE�ƁA��p�҂ɋ�Ƃ̎O�j�E�O�Ђ��I�ꂽ���ƂƊW���[���B |
| �i�T�j | 1335 �N�i���� 2�j�C�k�������̎q�ł��鎞�s�����q����������}���ċ������C�������`��j���Ĉꎞ�I�Ɋ��q���x�z���ɒu�����ł����Ƃ����Ƃ������B |
| �P�@�����̗� �R�@���v�̗� |
�Q�@�����̕� �S�@�������� |
| �@�P�R�R�T�N�i�����Q�N�j�V���A�k�������̈⎙���s�������i�����̗��j�B �@���q���U�߂�ہA���s�R�͖\���J�ɏP��ꂽ�����啧�a�ɔ��܂����A�������܂�ĕ��m�T�O�O�l�����������̂��Ɠ`�����Ă��܂��B �@���s�����q���U�߂����ƂŁA�������`�͗H����Ă�����ǐe�����E�Q���āA���q��Ă��܂��B�@ |
���@�P
 |

| �i�U�j | ��������ɏ��㊙�q����������̕⍲���Ƃ��ď㐙�������C�����ꂽ�E�������Ƃ������B |
| �P�@�֓��Ǘ� �R�@�A�� |
�Q�@�Ǘ� �S�@���Ǘ� |
| �@�֓��Ǘ��́A��������Ɋ��q�{�̒������������q������⍲���邽�߂ɒu���ꂽ��E�B �@�Ǘ̂́A�������{���R�̕⍲�����E�B �@�A���́A���q���{�̎�����⍲�����E�B �@���Ǘ��́A�k�����@�Ƃ̎����B |
���@�P
| �i�V�j | �i���̗��ŁC���R�����`���ɓ����ꂽ���q�����͂��ꂩ�B |
| �P�@�������� �Q�@�������� |
�Q�@�������� �S�@�����`�� |
| �@�i���̗��́A���q�����̑����������A�������{�Z�㏫�R�E�����`���Ɗ֓��Ǘ́E�㐙�����ƑΗ����ċN�������킢�B |
���@�Q

�i�ʊ莛�j
| �i�W�j | 1936 �N�i���a 11�j�ɁC���q�ݏZ�̍�Ƃɂ���Č������ꂽ���q�y���N���u�̏����͂��ꂩ�B |
| �P�@������ �R�@�v���Y |
�Q�@��[�N�� �S�@��Ŏ��Y |
���@�R
�i���J���j
| �i�X�j | ���q�̊C�݉����𑖂邩�Ă̏Ó�L�����H�C���݂̍��� 134 �������J�ʂ����̂͂����B |
| �P�@1889 �N�i���� 22�j �Q�@1910 �N�i���� 43�j �R�@1930 �N�i���a 5�j �S�@1956 �N�i���a 31�j |
| �@�C�ݐ��𑖂鍑���P�R�S�����́A�P�X�T�U�N�i���a�R�P�N�j�ɏÓ�L�����H�Ƃ��ĊJ�ʂ��Ă��܂��B �@�Ó�L�����H�����݂����̂́A�P�X�W�U�N�i���a�U�P�N�j�܂ŁB�@ |
���@�S
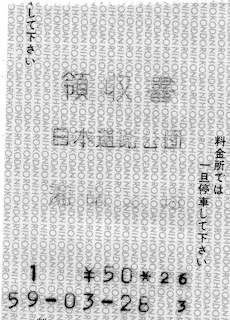
| �@���̗̎����́A���q��Ԃ̗������̂��̂ł��i���a�T�X�N�j�B |
| �i10�j | �]�ˎ���ɂ͕x�m�R��]�ތi���n�Ƃ��đ����̕����G�ɕ`����C�ŋ߂ł́u���{�̏��S�I�v�ɂ��I��Ă���̂͂ǂ����B |
| �P�@�a��]�� �R�@����� |
�Q�@�R�䃖�l �S�@�������l |
| �@�]�m�d�ԑ�����̌i�F���l�C���������l�́A�u���{�̏��S�I�v�ɑI��Ă��܂��B |
���@�S
| �i11�j | ���͓x�d�Ȃ�ЂȂǂŎ���ꂽ���C���B���������z��������̒������̓�K�哰�i�咷���@�j��͂��Č��������n�������s��Ȏ��ł������i�������������̂͂ǂ����B |
| �P�@��q���{�Ղ̗��R �Q�@���q�{���� �R�@���_�_�Ёi�咬�j�t�� �S�@�Ɋy���� |
| �@�i�����́A���q���{�i�����̌䏊�E��q���{�j���S���̕��p�i�k���j�ɑn������܂����B �@���̏ꏊ�́A���q�{�̗���B �@�i�����́A�������A�щz���A���ʌ��@�Ȃǂ�͂��Č��Ăꂽ���@�B �@�����`�o�Ɖ��B�������̗썰����߂邽�߂Ɍ��������̂��Ɠ`�����Ă��܂��B �@���r�̌i�ς́A�F�������@���P�����O�̈����r�̂悤�ł������Ƒz�肳��Ă��܂��B �@�{���́A���������咷���@�i��K�哰�j��͂��Č��Ă�ꂽ�悤�ł����A�����Ɉ���ɓ��A��t�����]���A�O�ʂɂ͉��r�����c����Ă��邱�Ƃ���A�S�̂̃C���[�W�́A���ʌ��@���Q�l�ɂ����̂�������܂���B �@���ʌ��@�́A���B�������O��ڂ̏G�t���A�F���������@�P������͂��Č��Ă����@�������Ƃ����܂��B |
���@�Q
 |



| �i12�j | ��䓰���̉��𗬂�銊�삪�Â��͍��T��Ƃ���ꂽ�̂́C����ɂ��Ȃ�ł��B |
| �P�@���@ �R�@���o |
�Q�@�E�� �S�@��C |
| �@��䓰�����Ԃɂ́A���o��l���~���̔肪���Ă��Ă��܂��B �@�ɓ����������Əo��A���������߂��Ƃ������o�̉��~�́A�������䏊�̓�A��䓰�i�������@�j�̐��ɂ������̂��Ƃ����܂��B |
���@�R
| �i13�j | ���@�U���|�����߂��ɂ���̂͊��q�\���̂����ł͂ǂꂩ�B |
| �P�@�̃m�� �R�@�ً��� |
�Q�@���i�� �S�@�j���� |
| �@���@�U���|���̔������Ă��Ă���͈̂�K��B �@�̃m���͓�K���i����X���j�A���i�����߉������{�̎Q����{��H�A�ً����͌䐬���A�j�������������l�ɒ����Ɋy����ɉ˂���ꂽ���B |
���@�S
 |

| �i14�j | ���q�\��� 1 �ł��鐯�m��́C�ǂ̐ؒʂ̓o����ɂ��邩�B |
| �P�@�T���J�� �R�@�Ɋy���ؒ� |
�Q�@�啧�ؒ� �S�@�����C�� |
| �@���m���́A���q�]�m���X���̗��l�̍A���������Ƃ�����ˁB �@������̋A�������ƍN������������̂��Ɠ`�����Ă��܂��B �@�Ɋy���ؒ��̓����A�����̉��ɂ���܂��B |
���@�R
 |

| �i15�j | �������������́C�����i�������镐�����a���������̌��̂��������Ƃ����N�����ł��邪�C�a��ꂽ�����͂��ꂩ�B |
| �P�@���꒩�� �R�@�㑍��L�� |
�Q�@���i�e �S�@���@�� |
| �@�������������́A���Γސؒ��̊┧����N���o�����q�ܖ����̈�B �@�P�P�W�R�N�i���i�Q�N�j�A�������̖������㑍��L�����������i���������̌��̂��������Ƃ����`�����c����Ă��܂��B |
���@�R

| �i16�j | �ȑO�͌�������O�ɂ��������C���݂͕����̕~�ɂ��̈ʒu��������Ă���݂̂ŁC��������́w���q���L�x��u�����������G�}�v�ɕ`����Ă��������Ƃ������B |
| �P�@���@� �R�@�ØI�� |
�Q�@������ �S�@�s�V�� |
| �@����������Ҏ[�������w�V�Ҋ��q�u�x�ɂ́u�������̐��O��̑O�ɂ���v�Ə�����Ă��܂��B |
���@�Q

| �i17�j | �w��ȋ��x�Ɂu�O���B�T�呒�����B�̉E�叫�Ɓi�������j�@�ؓ��̓��̎R��������ĕ���ƂȂ��v�Ƃ��邱�Ƃ���C�@�ؓ����ׂ̎R�̒����ɕ揊������Ƃ����u�O���B�T��v�Ƃ͂���̂��Ƃ��B |
| �P�@�k������ �R�@�k���d�� |
�Q�@�k���`�� �S�@�k��� |
| �@�Q�O�O�T�N�i�����P�V�N�j�A�����������ׂ̎R�̒��������k���`���̂��̂ƍl������@�ؓ��Ղ����@����Ă��܂��B |
���@�Q
| �i18�j | ���q����ɂ͒߉������{�̓����́u�؈ዴ�v���������C�{�o���O��ʂ�C�ޖ؍��܂ł̓��Ƃ���C���݂͖{�o����O�ɂ���Γ������k�̕������w����H�����Ƃ������B |
| �P�@������H �Q�@����H |
�Q�@�咬��H �S�@��K����H�@ |
| �@������H�́A�߉������{�̎Q����{��H�̓�������s���A�؈ዴ����������A�{�o���̖�O��ʂ�A�咬��H�����f�A������n�����ޖ؍��܂Œʂ��銙�q�̊���H�ł����B |
���@�P


| �i19�j | ���݁C�����H�͚敟����O�t�߂���ǂ��܂ł��������B |
| �P�@�߉������{ �R�@�R�䃖�l |
�Q�@�Z�n�� �S�@�䐬���w�Z |
| �@�����H����{��H�ƕ��s����H�B �@����������Ҏ[�������w�V�Ҋ��q�u�x�ł́A�敟���̖�O�����m�������F�_���܂ł̘H�Ƃ���Ă���悤�ł����A���݂ł��Z�n���Ɏ���܂ł̓����u�����H�v�ƌĂ�ł���悤�ł��B |
���@�Q


| �i20�j | ��m���̒n���̗R���́C����ؒʂ̉��ɂ���n��ł��邩��Ƃ���邪�C����ؒʂƂ͂ǂ��̂��Ƃ��B |
| �P�@���z�ؒ� �R�@�啧�ؒ� |
�Q�@�Ɋy���ؒ� �S�@�߉ޓ��ؒ� |
| �@��m���Ƃ����n���́A���q�����̈���Ɋy����ؒ��̉��ɂ��邱�Ƃɂ��Ƃ���Ă��܂��B |
���@�Q
| ���R�E�i�ς̖�� |
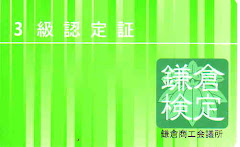
��P�R��R���g�b�v

�i�R���E�Q���E�P���̖��Ɖ���j
| �����q����̎��\�����݂� ���q���H��c���z�[���y�[�W�� |
�i���q���g�b�v�j
|
|