 |
 |
 |
 |
第18回鎌倉検定試験3級
《祭り・行事の問題》
|
|
| 鎌倉の祭り・行事に関する記述について,最も適当なものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| (81) | 2024年(令和6)7月17日に開催された鎌倉花火大会は,今回で何回を迎えたか。 |
| 1 61回 2 65回 3 72回 4 76回 |
答 4
| (82) | 新年を迎える深夜に,観音堂横の寺庭一面に置かれた,約5000基の祈願ロウソクに灯が点され、僧侶が新しい年の国家の安寧,五穀豊穣とともに,参拝者の除災招福を祈願し,読経する万灯祈願会が行われる寺院はどこか。 |
| 1 光明寺 2 円覚寺 3 建長寺 4 長谷寺 |
答 4
| 長谷寺は大晦日の23時に開門。 新年を迎えると、観音堂で「修正会」が行われ、その後、僧侶がさくら広場に集まり、万灯祈願会が行われます。 |


| (83) | 特に商売繁盛の御利益が大きいといわれることから,銭洗弁財天宇賀福神社への商業関係者の参拝が多くなるのはいつか。 |
| 1 初子の日 2 初巳の日 3 初午の日 4 初未の日 |
答 2
| 銭洗弁財天宇賀福神社の祭神は、本宮が市杵島姫命、奥宮が弁財天(宇賀神)。 2025年(令和7年)は巳年! 巳は蛇!蛇は弁財天の使い。 巳の日には蛇が弁財天に願いを届けてくれる! 2025年(令和7年)の初巳の日は1月12日。 |


| (84) | 毎年1月4日に腰越漁港で行われる漁師による仕事始めの行事を何というか。 |
| 1 船祝い 2 船おろし 3 潮神楽 4 汐まつり |
答 1
| 船おろしと船祝いは漁師さんの仕事始め。 船おろしは1月2日に坂ノ下海岸と材木座海岸で行われます。 船祝いは1月4日に腰越漁港で行われます。 |

| (85) | 毎年1月8日に白山神社で行われる大注連祭では,毘沙門天の使いを模したものが奉納されるが,それは何か。 |
| 1 蛇 2 百足 3 鼠 4 虎 |
| 白山神社の大注連祭は「むかでしめ」とも呼ばれています。 |
答 2
| 白山神社は、源頼朝が京都の鞍馬寺から賜った毘沙門天を安置するために建立した毘沙門堂が始まり。 大注連祭では、毘沙門天の使いとされるハガチ(百足(ムカデ))を模した6メートルにもなる大注連縄(大百足)が奉納されます。 |
| (86) | 毎年1月10日に本えびすを催し,商売繁盛を祈願し,福娘により福銭,福笹,御神酒が振る舞われる寺社はどこか。 |
| 1 銭洗弁財天宇賀福神社 2 明王院 3 荏柄天神社 4 本覚寺 |
答 4
| 本覚寺の鎌倉えびすは、正月1日から3日まで初えびす、10日に本えびす。 |

| (87) | 毎年2月8日に荏柄天神社で行われる行事で供養されるものは何か。 |
| 1 使い古した針 2 使い古した鋏 3 古筆 4 古くなった人形や玩具 |
| 2月8日は針供養の日。 |
答 1
| 荏柄天神社では、使い古した針にねぎらいと感謝を込めて、拝殿前の三方の上に置かれた豆腐に針を刺して供養します。 針供養の頃は、古代青軸が見ごろになる頃。 |
| (88) | 毎年春,花見の季節に見事な桜並木が楽しめる若宮大路の二の鳥居から三の鳥居までの約500メートルの参詣路を特に何というか。 |
| 1 花参道 2 段葛 3 桜大路 4 中の道 |
| 若宮大路の二の鳥居から三の鳥居まで続く道は段葛。 |
答 2
| 今日では「桜の名所」として知られる段葛は、かつては何も植えられていない道でした。 桜が植えられたのは、1918年(大正7年)の頃。 現在の桜は、2014年(平成26年)からの整備工事によって植え替えられたもの。 |

| (89) | 毎年4月第3土曜日に行われる義経まつりでは,源義経の遺徳をしのぶ法会が行われたあと,パレードするのはどこか。 |
| 1 若宮大路 2 腰越商店街 3 由比ヶ浜・佐助一帯 4 坂ノ下町内 |
| 義経まつりは、源義経ゆかりの満福寺がある腰越で行われるイベント。 |
答 2
| 義経まつりは、源義経の偉業を偲ぶ祭。 ここ数年は開催されていませんが・・・ 満福寺で義経慰霊法要が行われた後、パレードが龍口寺前から腰越天王屋敷(小動神社)まで進みます。 |
| (90) | 宝戒寺では,毎年5月,北条氏を供養し弔うために( )大権現会が行われる。( ) にあてはまるのはどれか。 |
| 1 公方 2 執権 3 徳崇 4 管領 |
| 5月22日は、鎌倉幕府滅亡の日。 宝戒寺では徳崇大権現会が営まれます。 徳崇大権現とは、北条高時のこと。 |
答 3
| 宝戒寺は、後醍醐天皇が滅亡した北条氏の菩提を弔うため、足利尊氏に命じて建立させました。 徳崇大権現会では、徳祟大権現堂の北条高時の木像を本堂に移して大般若経が転読されます。 |



| (91) | 建長寺で,梶原景時を慰霊するために施餓鬼会が行われる場所はどこか。 |
| 1 総門 2 三門 3 仏殿 4 法堂 |
| 建長寺では、毎年7月15日、三門(山門)で「三門施餓鬼会」と梶原景時の亡霊を弔うための「梶原施餓鬼会」が行われます。 |
答 2
| 建長寺が開かれて間もない7月15日の施餓鬼会が終了した直後、梶原景時の亡霊が現れたのだといいます。 三門梶原施餓鬼会は、その時から行われているそうです。 |
(静岡市:梶原山)
| 梶原景時は平家方にありながら、石橋山の戦いに敗れて山中に逃げ込んだ源頼朝を助けたといわれる武将。 頼朝に重用されましたが、頼朝亡き後に鎌倉を追放され、上洛途上の駿河国清見関で最期をとげました。 終焉の地である梶原山の碑に刻まれている「鎌倉本體の武士 梶原景時終焉之地」は、建長寺管長の筆。 |


| (92) | 立秋の前日から8月9日の間,鎌倉在住の著名人の揮毫した多数のぼんぼりが境内に掲揚され,夕暮れとともに巫女により明かりが灯される神社はどこか。 |
| 1 鎌倉宮 2 荏柄天神社 3 八雲神社 4 鶴岡八幡宮 |
答 4

| ぼんぼりの掲揚は、最終日の源実朝の誕生日に行われる実朝祭に書画を奉納したことに始まるのだそうです。 |
| (93) | 光明寺で「十夜法要」を行うことを勅許した天皇はだれか。 |
| 1 伏見上皇 2 後花園天皇 3 後土御門天皇 4 後嵯峨上皇 |
| 光明寺のお十夜は、1495年(明応4年)に後土御門天皇より勅許されました。 |
答 3
| お十夜は、三日三晩にわたり本堂で念仏や御詠歌を唱える法会。 「千年間修行をすることよりも尊い」といわれています。 |
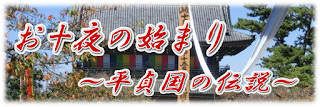
| (94) | 地獄に落ちた罪人を苦しみから救おうと,獄卒に代わって火を焚いたため黒くすすけたという黒地蔵を参拝する縁日が,覚園寺で行われるのはいつか。 |
| 1 5 月 22 日 2 7 月 15 日 3 8 月 10 日 4 8 月 16 日 |
| 鎌倉の8月10日は大功徳日。 覚園寺では黒地蔵の縁日、杉本寺・安養院・長谷寺では観音菩薩の縁日(四万六千日)となります。 |
答 3

| 黒地蔵縁日に参拝すると無尽蔵の御利益を得ることができるのだとか。 |
| (95) | 鶴岡八幡宮と鎌倉宮では,大祓式が年に2回行われるが,それは大晦日といつか。 |
| 1 5 月 31 日 2 6 月 30 日 3 7 月 31 日 4 8 月 31 日 |
| 大祓式は半年に一度行われる神事。 |
答 2
| 6月の大祓は、昔から「夏越祓」(なごしのはらえ)と呼ばれます。 鶴岡八幡宮では、舞殿前に茅萱(ちがや)で作った「茅の輪」が設けられ、茅の輪くぐりが行われます。 |
|
|
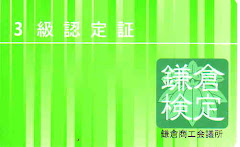

(3級・2級・1級の問題と解説)
| ★鎌倉検定の受検お申し込みは 鎌倉商工会議所ホームページへ |
(鎌倉情報トップ)
|
|