 |
覚 園 寺
北条義時の大倉薬師堂
|
|
| 覚園寺(かくおんじ・真言宗泉涌寺派)は、1218年(建保6年)、二代執権北条義時の建てた大倉薬師堂を前身とする寺院。 焼失後の1296年(永仁4年)、九代執権北条貞時が元寇が再び起こらぬようにとの願いから覚園寺を創建。 開山には忍性の弟子智海心慧が迎えられ、真言・律・禅・浄土の四宗兼学の道場となった。 山号は鷲峰山(じゅぶせん)。 鎌倉幕府滅亡後も後醍醐天皇の勅願所、足利尊氏の祈願所となって保護を受け、鎌倉最大の茅葺の薬師堂では尊氏自筆の梁牌(棟札)を見ることができる。 大悲殿跡地には、江戸時代の古民家で、手広にあった内海家の住宅が移築されている。 裏山には「百八やぐら」と呼ばれるやぐら群がある。 1871年(明治4年)に出された兼宗廃止令により、真言・律・禅・浄土の四宗兼学から真言宗に改められている。 |
| 鎌倉十三仏第11番札所 (阿しゅく如来) 鎌倉地蔵巡礼第3番札所 (黒地蔵) |
| 開山 | 智海心慧 |
| 開基 | 北条貞時 |
| 本尊 | 薬師如来 |
| ※ | 『吾妻鏡』によれば、大倉薬師堂の薬師如来像・十二神将像は運慶の作であったのだという。 |
鎌倉の真言宗の寺
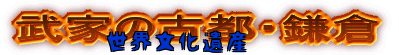
 |
(仏殿) |
(黒地蔵) |



| 鎌倉十井「棟立ノ井」 (むなたてのい) |
| 薬師堂背後の山ぎわにある横井戸。 家屋の棟立(破風)のような石の下から湧いているのでこの名がある。弘法大師が井戸を掘り、仏に奉納する水を汲んだと伝えられる。拝観することはできない。 別名→破風ノ井(はふうのい) (参考:鎌倉十井) |
| 開山塔と大燈塔 |
| 薬師堂の奥にある開山智海心慧と二世大燈源智の墓。 どちらも国の重要文化財に指定されている安山岩製の宝篋印塔。拝観はできない。 |
| 十三仏やぐら |
| 大きなやぐらの内部には、十三仏信仰に基づく石仏が祀られている。 人はその死後、十三の仏が姿を変えた十三王によって裁決されるとされている(参考:鎌倉十三仏)。 十三仏信仰は鎌倉時代末頃より始まった。 |
| 願行と智海心慧 |
| 大楽寺を開いた願行(京都泉涌寺第六世)は、真言・律・禅・浄土の四宗を修めた高僧。 覚園寺開山の智海心慧は、京都泉涌寺にいた願行から密を受け、極楽寺の忍性に戒律を受けたといわれている。 したがって、覚園寺も四宗兼学の寺院だった。 理智光寺、大町の安養院も願行が開いたとされる寺で、扇ヶ谷の浄光明寺の愛染明王像、玉縄の玉泉寺の胎内不動は願行作と伝えられている。 願行は鎌倉に泉涌寺派を伝えた人物で、弟子の智海心慧がそれを開花させた。 愛染堂に安置されている「鉄造不動明王坐像」は「試みの不動」と呼ばれ、願行が江ノ島に参籠して大山寺の鉄造不動明王像を鋳造したときに、試しに鋳造したものと伝えられている(参考:江ノ島岩屋)。 |
| 大山寺の鉄造不動明王は、毎月8・18・28日と11月8日〜12月8日に開催されるもみじ祭りで開帳されている。 |
(鎌倉アルプスを散策)
| 総門跡の庚申塔からはハイキングコース。 百八やぐらや弘法大師八十八箇所霊場がある。 |
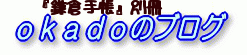
| 大師堂〜覚園寺参道〜 鎌倉アルプスの散策・・・前編 後編 |

(北条氏ゆかりの寺社・史跡)
覚園寺
| 鎌倉市二階堂421 0467(22)1195 鎌倉駅から「大塔宮」行バス終点下車 徒歩10分 |
鶴岡八幡宮周辺・西御門・二階堂
| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |
(鎌倉情報トップ)
 |
 |
 |
 |
 |
|
|