 |
鎌倉の右大臣の家集
金 槐 和 歌 集
|
|
| 『金槐和歌集』は、三代将軍源実朝が編纂した家集。 「金」は「鎌倉」の鎌の字の「かねへん」を表し、「槐」には「大臣」という意味があることから、別名『鎌倉の右大臣(源実朝)の家集』と呼ばれています。 |
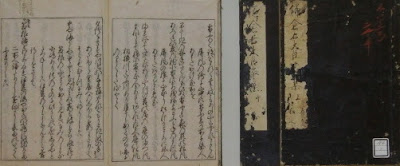
| 源実朝は、『新古今和歌集』の撰者藤原定家に師事しました。 『金槐和歌集』は『鎌倉右大臣家集』とも呼ばれ、定家から『万葉集』が贈られた1213年(建保元年)頃に成立した自撰のものと考えられています。 |
〜歌人実朝〜
| 1203年(建仁3年)、源実朝は、兄頼家が失脚したことによって12歳で征夷大将軍となりました。 翌年には後鳥羽上皇の従兄妹・坊門姫(西八条禅院)と結婚。 父頼朝を尊敬し、その言行を学ぶなど多くの御家人から慕われていました。 『吾妻鏡』によると、和歌に関心をもった実朝は、1205年(元久2年)に十首の和歌を作っています。 この年、父頼朝の歌が入集している『新古今和歌集』の筆写も取り寄せました。 『新古今和歌集』は、後鳥羽上皇の命によって編纂された勅撰和歌集。 そして、1206年(承元3年)から本格的に和歌の勉強を始めたのだといいます。 1209年(承元3年)には、和歌の神・住吉大社に二十首の和歌を奉納するとともに、十首の和歌を藤原定家に送って批評を願っています。 1211年(建暦元年)に鎌倉を訪れた鴨長明は、度々実朝を訪問したといいます。 この時、長明は、頼朝の法華堂にも赴き「草も木も靡きし秋の霜消えて空しき苔を払う山風」と詠んでいます。 実朝の歌は、強い実感を率直に表した「万葉調」のものが多く、藤原定家より贈られた『万葉集』がその基礎となっているようです。 |
〜源実朝の和歌めぐり〜
| 以下に紹介する歌は実朝の代表的な歌ですが、『金槐和歌集』に載せられていない歌も含まれています。 |
| 山はさけ海はあせなむ世なりとも君にふた心わがあらめやも |
| 後鳥羽上皇への恭順の意を表した歌。 関東大震災で倒壊した鶴岡八幡宮の二の鳥居の柱に彫られています(鎌倉国宝館前に建てられています。)。 |

| 大海の磯もとどろに寄する波われてくだけてさけて散るかも |
| 相模の海を歌った男性的なもので潔さや清らかさが伝わってくる歌です。 どこから見た海かは不明ですが・・・。 |
| 古寺のくち木の梅も春雨にそぼちて花もほころびにけり |
| 源頼朝が父の菩提を弔うために建立した勝長寿院の梅を詠んだ歌。 |
| ちはやぶる伊豆のお山の玉椿八百万代も色はかはらし 箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波のよるみゆ たまくしげ箱根のみうみけけれあれや二国かけてなかにたゆたふ 伊豆の国や山の南に出づる湯の速きは神の験なりけり 都より巽にあたり出湯あり名は吾妻路の熱海といふ |
| いずれも伊豆・箱根の二所詣に出掛けたときに詠んだ歌です。 |
(箱根神社) |
 |
| 時により過ぐれば民の嘆きなり八大龍王雨やめたまへ |
| 1211年(建暦元年)の洪水の被害に際して、「恵みの雨も過ぎると民は嘆くことになる」ので、雨を司る八大龍王に祈念して詠まれた歌。 実朝が祈念したのは大山の阿夫利神社ともいわれ、大山寺の倶利伽羅堂が八大龍王を祀った社だったのだといいます。 |
 (大山寺) |
| ものいはぬ四方のけだものすらだにもあはれなるかなや親の子をおもふ |
| 親が子を愛する光景を詠んだ歌です。 秦野市にある実朝の御首塚に碑が建てられています。 |

| 世の中はつねにもがもななぎさこぐあまの小舟の綱手かなしも |
| 『小倉百人一首』に選ばれた歌。 「世の中が変わらないで欲しい」という実朝の思いが込められた歌です。 |
(鎌倉海浜公園)
| しほがまの浦の松風かすむなりやそしまかけて春や立つらん |
| 古くより歌枕の地として知られた陸奥国の塩竈を詠んだ歌。 |
(宮城県塩竃市)
| 風さわぐをちの外山に雲晴れて桜にくもる春の夜の月 |
| 鶴岡八幡宮の流鏑馬馬場に植えられている実朝桜の碑に載せられている歌です。 |
| こむとしもたのめぬうはの にたに秋かせふけば 雁はきにけり いま来むとたのめし人は見えなくに秋かせ寒み雁はきにけり |
| 帰国してなかなか戻らない近臣の東重胤に早く帰参するよう催促するために詠んだ歌。 |
| 君が代も我が代も尽きじ石川や瀬見の小川の絶えじとおもへば |
| 鴨長明の「石川や瀬見の小川の清ければ月も流れも尋ねてぞすむ」を本歌とした歌。 瀬見の小川は、京都の下鴨神社が鎮座する糺の森を流れる川。 |

| 夕されは秋風涼したなばたの天の羽衣たちや更ふらん 彦星の行合をまつ久方の天の河原に秋風ぞ吹く |
| 七夕を詠んだ歌。 |
(鶴岡八幡宮)
| 桜花ちりかひかすむ春の夜のおぼろ月夜のかもの川風 |
| 京都の鴨川には『新古今和歌集』を編纂させた後鳥羽上皇や『金塊和歌集』を編んだ源実朝の歌碑が建てられています。 |
〜和歌と政治〜
| 源実朝は、「実権を北条政子や北条義時に握られ、和歌にふけるようなった」という批判的な評価がされがちですが・・・ 和歌は、曲節をつけて詠み上げられます(披講)。 これには、神仏と交感して、天下泰平・国土安穏を願うという意味があるのだそうです。 後鳥羽上皇は、蹴鞠や和歌を極めた人でした。 実朝にとって和歌は、後鳥羽上皇と良好な関係を築くうえで不可欠なものだったと考えられます。 尊敬する父頼朝の和歌にも優れ、『新古今和歌集』に撰されています。 |
| 十二所にあったという大慈寺は、実朝が後鳥羽上皇への恩と父頼朝の徳をたたえるために創建した寺だったと伝えられています。 |
〜伝説:歌ノ橋〜
| 荏柄天神社には、実朝の伝説が残されています。 1213年(建保元年)、泉親衡の謀反が発覚し、捕えられた者の中に渋川兼守という人物がいました。 兼守は謀反の罪を晴らそうと荏柄天神社に和歌十首を奉納します。 その和歌を手にした実朝は、感動して罪を許したのだと伝えられています。 兼守がそのお礼にと架けた橋が、金沢街道に架けられている「歌ノ橋」なのだそうです。 |

泉親衡の乱が発端となった合戦

〜最後の歌〜
| 出でて去なばぬしなき宿となりぬとも軒端の梅よ春を忘るな |
| この歌は、実朝が暗殺された日に詠まれたと伝えられているもの。 1219年(承久元年)1月27日、実朝は、甥の公暁(兄頼家の子)によって暗殺されてしまいます。 実朝が暗殺されたのは、鶴岡八幡宮で行われた右大臣拝賀の式後のことでした。 拝賀式に出掛けるとき、実朝はこの歌を詠んで、髪を結ってくれた者に髪の毛を与えて出て行ったと伝えられています。 「二度と戻れないことを知っていたのではないか?」と思わせる悲しい歌です。 『金槐和歌集』に載せられている歌ではありませんし、実朝が詠んだ歌であるという確証もありませんが、実朝の悲劇を伝える歌として知られています。 |
〜恋の歌〜
| 月影のそれかあらぬかかげろふのほのかに見えて雲がくれにし |
| 実朝の恋の歌。 実朝が暗殺された後、正妻の坊門姫(西八条禅院)は出家して京都に戻り、実朝の菩提を弔うために大通寺(万祥山遍照心院)を建立しています。 |
(京都)

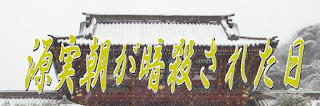
〜実朝を偲ぶ祭事〜

| 3月の「献詠披講式」は、和歌に優れた源頼朝と源実朝を偲んで行われる神事。 |
| 8月の「ぼんぼり祭」の最終日は、源実朝の誕生日。 白旗神社で「実朝祭」が行われます。 「吹く風の涼しくもあるかおのづから山の蝉鳴きて秋は来にけり」 |
| 10月28日には、白旗神社で源実朝の遺徳を偲ぶ「文墨祭」が行われます。 |

2022年のNHK大河ドラマ

(鎌倉情報トップ)
 |
 |
 |
 |
 |
|
|