 |
 |
 |
 |
第18回鎌倉検定試験3級
《芸術・文化の問題》
|
|
| 鎌倉の芸術・文化に関する記述について,最も適当なものを 1 ~ 4 から選びなさい。 |
| (56) | 2024年(令和6)に新たに国の登録有形文化財に登録された,旧鎌倉図書館はどこにあるか。 |
| 1 御成町 2 雪ノ下 3 二階堂 4 長谷 |
| 鎌倉市役所の敷地に建てられています。 |
答 1

旧鎌倉図書館
| (57) | 円覚寺の釈(洪嶽)宗演に師事し,哲学として禅の研究を深め,禅を世界に広めることに尽力した人物はだれか。 |
| 1 三木卓 2 津田左右吉 3 和辻哲郎 4 鈴木大拙 |
| 円覚寺の釈宗演に師事した鈴木大拙は、『大乗起信論』を英訳出版し、『大乗仏教概論』を著して禅の思想を海外に広めました。 晩年は、自らが東慶寺境内に設立した松ヶ岡文庫で研究を行っていました。 |
答 4

| (58) | 次のうち,鎌倉市にある建造物で国宝であるものはどれか。 |
| 1 白旗神社社殿 2 建長寺三門 3 円覚寺舎利殿 4 鶴岡八幡宮本宮 |
| 鎌倉で国宝に指定されている建造物は円覚寺の舎利殿のみ。 |
答 3
| 舎利殿は、円覚寺塔頭正続院の昭堂。 現在の舎利殿は、鎌倉尼五山の一つ太平寺の仏殿が移築されたもの。 鎌倉幕府三代将軍の源実朝が宋から請来したという仏牙舎利が祀られています。 仏牙舎利は、源実朝が創建した大慈寺に納められていましたが、九代執権北条貞時が円覚寺に創建した祥勝院に移したのだと伝えられています。 正続院は祥勝院を始まりとしています。 円覚寺の仏舎利は、室町時代、その一部が京都に献じられ、鹿王院の舎利殿に安置されている仏舎利は円覚寺にあったものだと伝えられています。 2024年(令和6年)、京都の嵐電と鎌倉の江ノ電の姉妹提携15周年記念の記念事業「あたらしいコトみつけよう」がスタート。 第1回は「円覚寺舎利殿・鹿王院舎利殿」でした。 |
| (59) | 次の「頂相(名僧の肖像画)」のうち,唯一国宝に指定されているのはどれか。 |
| 1 建長寺正統院「高峰顕日坐像」 2 瑞泉寺「夢窓国師坐像」 3 建長寺「蘭渓道隆像」 4 円覚寺「仏光国師坐像」 |
答 3

| 建長寺の「絹本淡彩蘭渓道隆像」は、蘭渓道隆58歳のときの頂相の像で文永8年(1271年)の自賛があります。 |
| (60) | 次の梵鐘のうち,国宝であり,平安時代後期にならった復古調のデザインが特徴であるものはどれか。 |
| 1 建長寺鐘 2 常楽寺鐘 3 円覚寺鐘 4 長谷寺鐘 |
| 建長寺、円覚寺、常楽寺の鐘は、鎌倉三名鐘と呼ばれています。 長谷寺の鐘を含めると鎌倉四古鐘とも。 国宝に指定されているのは、建長寺梵鐘と円覚寺梵鐘。 平安時代の作風を踏襲しているのは建長寺梵鐘。 |
答 1
| 建長寺の梵鐘は、北条時頼が大旦那となって鋳造されたもので、開山の蘭渓道隆が銘文を撰しています。 鋳物師は、高徳院の大仏鋳造も手掛けたとされる物部重光。 |
| (61) | 次のうち,神奈川県の無形民俗文化財に指定されているものはどれか。 |
| 1 鶴岡八幡宮の流鏑馬 2 御霊神社(坂ノ下)の面掛行列 3 鶴岡八幡宮舞殿の静舞 4 材木座の鎌倉天王唄 |
| 坂ノ下の御霊神社の神幸祭では、神奈川県の無形民俗文化財に指定されている面掛行列を観ることができます。 |
答 2
| 御霊神社の面掛行列は、鶴岡八幡宮の放生会で行われていた面掛行列に倣ったものといわれています。 |

(東京国立博物館蔵)

| 円覚寺の弁財天祭礼洪鐘祭でも面掛行列がありました。 2023年10月29日に開催された洪鐘祭では、八雲神社の面掛行列も参加しています。 |
| (62) | 藤原定家に師事し,『金槐和歌集』を編んだ鎌倉幕府の将軍はだれか。 |
| 1 源頼家 2 源実朝 3 藤原(九条)頼経 4 藤原(九条)頼嗣 |
| 『金槐和歌集』を編んだのは、三代将軍源実朝。 |
答 2
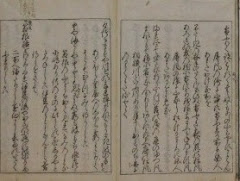
| 『金槐和歌集』は『鎌倉右大臣家集』とも呼ばれ、藤原定家から『万葉集』が贈られた1213年(建保元年)頃に成立した自撰のものと考えられています。 「世の中は つねにもがもな なぎさこぐ あまの小舟の 綱手かなしも」 この歌は、藤原定家の『小倉百人一首』に選ばれています。 |
=源実朝の歌碑=
 |
(熱海) |
 (熱海) |
(宮城県塩竃市) |
(京都) |
| (63) | 息子冷泉為相の領地相続をめぐる訴訟のために,京都から鎌倉に下り,月影ヶ谷に住み,その日々を『十六夜日記』に著した人物はだれか。 |
| 1 和泉式部 2 阿仏尼 3 後深草院二条 4 覚山尼 |
| 冷泉為相は藤原定家の孫。 鎌倉に下ったのは、母の阿仏尼。 |
答 2
 |
 |
| 『十六夜日記』は、京都から鎌倉への道中と鎌倉に滞在中のことを記した紀行文。 「あづまにてすむ所は 月かげのやつとぞいふなる」 鎌倉に下った阿仏尼は、極楽寺近くの月影ヶ谷に住んだのだといいます。 息子の為相も母を慕って鎌倉に下って藤ヶ谷に住みました。 浄光明寺の裏山には、冷泉為相墓と伝わる供養塔があります。 |
| (64) | 夏目漱石が参禅し,漱石の「佛性は白き桔梗にこそ…」の句碑が今に残る円覚寺の塔頭はどこか。 |
| 1 桂昌庵 2 黄梅院 3 帰源院 4 龍隠庵 |
| 1894年(明治27年)末から翌年にかけて円覚寺の塔頭起源院に止宿した作家夏目漱石は、釈宗演に参禅し、その体験は小説『門』に描かれました。 |
答 3
 |
| 帰源院は、円覚寺第三十八世傑翁是英の塔所。 境内には、夏目漱石の句碑「仏性は白き桔梗にこそあらめ」が建てられている。 |

| (65) | 2000年(平成12)に閉鎖されるまで,小津安二郎監督の『晩春』や山田洋次監督の『男はつらいよ』シリーズなど多くの名作を生み出した松竹の撮影所があったのはどこか。 |
| 1 腰越 2 玉縄 3 大船 4 山崎 |
| 1936年(昭和11年)、松竹撮影所は蒲田から大船に移転しています。 |
答 3

| 小津安二郎は浄智寺の近くに住んでいました。 円覚寺には墓があります。 |
| (66) | かつては風俗画を得意とした鏑木清方の住居があったことから,現在鎌倉市鏑木清方記念美術館があるのはどこか。 |
| 1 小町 2 雪ノ下 3 二階堂 4 十二所 |
| 鏑木清方は、雪ノ下にアトリエを構えました。 |
答 2

| 鏑木清方記念美術館は、アトリエと住宅跡に開館。 |
| (67) | もとは1936 年(昭和11)に旧加賀藩前田家16代当主前田利為により建築された長谷にある別荘で,鎌倉市に寄贈され,1985年(昭和60)から現在のように利用されている施設は何か。 |
| 1 鎌倉文学館 2 鎌倉芸術館 3 鎌倉歴史文化交流館 4 鎌倉市長谷子ども会館 |
答 1
| 鎌倉文学館は、内閣総理大臣・佐藤栄作が別荘として利用し、三島由紀夫は『春の雪』に描いています。 |
| (68) | 鎌倉市の景観重要建築物等に指定されている「野尻邸」は,だれの邸宅だったものか。 |
| 1 里見弴 2 諸戸静六 3 久米正雄 4 大佛次郎 |
答 4

| 旧大佛次郎茶亭は、野尻邸(旧大佛次郎茶亭)として「鎌倉市景観重要建築物等」に指定されていましたが、2019年(平成31年)、維持管理の関係で売却が決定され、2020年(令和2年)から一般社団法人大佛次郎文学保存会が継承しています。 |

| (69) | 源頼朝が鶴岡八幡宮を造営・再建したときに,多くの木材を材木座海岸から境内まで運ぶ際に行われていたとされる芸能は何か。 |
| 1 鎌倉木遣唄 2 鎌倉神楽 3 鎌倉囃子 4 鎌倉天王唄 |
| 源頼朝が鶴岡八幡宮を造営した際、材木座海岸に引き上げられた木材は「天王唄」を歌いながら運ばれたといいます。 |
答 4
 |
| 1月11日に材木座海岸で行われる潮神楽では、鎌倉天王唄が奉納されます。 1月4日の鶴岡八幡宮の手斧始式では、鎌倉木遣唄を唄いながら御神木が運ばれます。 |
| (70) | 「フクちゃん」で国民的な人気を博し,鎌倉駅西口に近い御成町に長く住んだ漫画家はだれか。 |
| 1 横山光輝 2 那須良輔 3 横山隆一 4 清水崑 |
| 数年前まで鶴岡八幡宮の平家池畔には「フクちゃんちのハクモクレン」が植えられていました。 由比ヶ浜の駐車場から観光客を市中心地に運ぶバスは「フクちゃん号」。 |
答 3
| 荏柄天神社の絵筆塚は、横山隆一らが建立したもの。 |
|
|
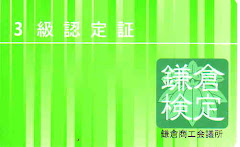

(3級・2級・1級の問題と解説)
| ★鎌倉検定の受検お申し込みは 鎌倉商工会議所ホームページへ |
(鎌倉情報トップ)
|
|