大和国 長谷寺
|
|
| 奈良(大和国)の長谷寺(はせでら)は、686年(朱鳥元年)、興福寺の僧・道明が天武天皇の病気平癒のため鋳造した銅板法華説相図(千仏多宝仏塔)を安置したことに始まるのだと伝えられている。 のちの727年(神亀4年)、東大寺開山の良弁の弟子・徳道が聖武天皇の勅命により、近江国で流れ出た霊木で造立した十一面観音像を安置。 行基を導師として観音堂の供養が行われたのだという。 ただ、長谷寺の創建については諸説あり、いずれも伝承の域を出ない。 本尊は十一面観世音菩薩。 東大寺や興福寺の末寺だった時代もあったが、1588年(天正16年)、専誉が入山したことで真言宗豊山派の総本山となる。 新義真言宗の総本山・根来寺の学頭だった専誉は、豊臣秀吉により根来寺が焼討ちされると、高野山・醍醐寺などに移ったが、秀吉の弟で郡山城主だった豊臣秀長の招きで衰退していた長谷寺に招聘されたのだという。 |
| ※ | 徳道の師は道明ともいわれるが詳細は不明。 |

〜初瀬詣〜
| かつて長谷寺の地は「豊初瀬」(とよはつせ)・「泊瀬」(はつせ)と呼ばれ、長谷寺も初瀬寺・泊瀬寺・豊山寺とも呼ばれていた。 長谷寺は平安時代になると貴族の信仰をあつめ、藤原道長が参詣。 清少納言・紫式部・赤染衛門・菅原孝標女も訪れ、『枕草子』・『源氏物語』・『赤染衛門集』・『更級日記』に登場させている。 彼女らの一世代前の文学者で藤原兼家の妻・藤原道綱母は、初瀬詣や石山詣を重ねて出産を祈ったのだという。 藤原実資も女児誕生を祈願して霊夢をみたのだという。 鎌倉時代には源頼朝の妻北条政子も参詣している。 |
〜西国三十三所の根本道場〜
| 徳道は、西国観音霊場三十三所巡礼の開祖。 そのため長谷寺は西国三十三所の根本道場と呼ばれ、長谷信仰は全国に広まった。 鎌倉時代に開設されたという坂東三十三箇所は、源頼朝の観音信仰と、源平の戦いで西国に赴いた坂東武者たちが西国三十三箇所の霊場を観たことに始まるのだという。 その後、観音巡礼は、西国三十三箇所、坂東三十三箇所に、秩父三十四箇所が加わり、百観音巡礼として発展した。 鎌倉の長谷寺は徳道が開いたと伝えられ、坂東観音巡礼の第八番札所となっている。 |
〜徳道と花山法皇〜
| 718年(養老2年)、仮死状態となった徳道は、地獄で閻魔大王のお告げを受けて西国観音霊場三十三所を定めたのだと伝えられている。 しかし、人々には受け入れられず、三十三所の宝印を摂津国の中山寺の石棺に納めたのだという。 それから約270年後、花山法皇がその石棺を探し出し、三十三の観音霊場を巡礼。 そのため、花山法皇は西国観音霊場三十三所の中興の祖と呼ばれている。 西国三十三所の御詠歌は、花山法皇が巡礼の際に木の短冊にしたためた和歌なのだとか。 長谷寺の御詠歌は 「いくたびも まいる心は はつせでら 山も誓いも 深き谷川」 |
(宝塚市) |
(中山寺の石棺) |
| 中山寺は源頼朝も信仰した我が国初の観音霊場。 宝印が納められた石棺は白鳥塚古墳の石の櫃。 |
(三田市) |
(三田市) |
| 花山院菩提寺は花山法皇が隠棲した地で、境内には花山法皇の御廟がある。 |
(国宝)
(重文) |
(重文) |
(重文) |
(重文)
| 法起院は、長谷寺の開山・徳道を祀る塔頭。 玉鬘神社は、紫式部の『源氏物語』登場する玉鬘を祀るために創始された。 |
〜大和長谷寺と鎌倉長谷寺〜
 |
 |
| 鎌倉の長谷寺は、736年(天平8年)の開創と伝えられ、開基は藤原房前、開山は徳道。 観音堂には大和国長谷寺の十一面観音と同じ長谷寺式十一面観音が安置されている。 |

| 鎌倉の長谷寺に伝えられる「長谷寺縁起絵巻」は、大和国長谷寺の草創と十一面観音造立の由来を描いたもの。 開基の藤原房前の援助を受けて徳道が十一面観音を造立し、行基によって開眼供養が行われたことなどが描かれている。 |
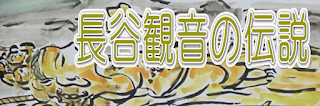
| 伝説によると・・・ 徳道が造立した十一面観音像は二体。 一体は大和国の長谷寺に置かれ、もう一体は海に流されて相模国の三浦半島に流れ着き、鎌倉に運ばれたのだという。 |
〜京都の大雲寺の十一面観音〜
| 紫式部ゆかりの京都大雲寺の本尊は行基作と伝わる十一面観音。 大和国長谷寺や鎌倉長谷寺の十一面観音像と同じ霊木で造立されたのだという。 |
〜菅原孝標女と長谷寺〜
| 菅原孝標女は、1046年(永承元年)10月25日、わざわざ後冷泉天皇即位の大嘗会の御禊の日に初瀬詣に出発している。 菅原孝標女の先祖は菅原道真。 「長谷寺縁起文」は、道真が執筆したと伝えられている。 「長谷寺縁起絵巻」にもその様子が描かれている。 |
〜後白河法皇の『梁塵秘抄』〜
| 後白河法皇は、観音菩薩の効験あらたかな寺として清水寺・石山寺・長谷寺・粉河寺(紀伊国)・西寺(近江国)・六角堂を挙げている。 |

長谷寺
| 奈良県桜井市初瀬731−1 近鉄大阪線「長谷寺駅」下車 徒歩15分 |
大和国長谷寺
| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |




 |
 |
 |
 |
|
|