 |
 |
 |
 |
第17回鎌倉検定試験1級
《記述式の問題その5》
|
|
| 次の文の〔 ① 〕,〔 ② 〕に最も適当な語句を書きなさい。ただし,〔 ① 〕,〔 ② 〕 両方できて正解とする。(各 2 点) |
| 〔 ① 〕は漢字で,〔 ② 〕は数字で書きなさい。 |
| (51) | 津の鎮守〔 ① 〕は江島神社とは夫婦神社とされ,〔 ② 〕年に一度行われる江島神社の還暦巳歳大祭には,故事にちなんで,祭神の五頭龍大神の御神体が江島神社に神奉され,弁財天像とともに特別開帳され間近で拝する事ができる。 |
| 津の鎮守は龍口明神社で、もとは片瀬の龍口寺の横にありました。 60年に一度行われる江島神社の大祭では神輿が江ノ島へ渡ります。 |
答 ① 龍口明神社 ② 60
 |
| 江の島縁起は、江の島の成り立ちと歴史を天女と五頭龍の伝説で表した絵巻物語。 夏のイベント・江の島灯籠では「天女と五頭龍」の灯籠も設置されます。 |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (52) | 作家川端康成が愛蔵した「十便図・十宜図」は,中国の文人李漁が詠んだ漢詩「伊園十便十二宜詩」を主題として江戸時代の文人画家〔 ① 〕と,俳人としても知られる文人画家〔 ② 〕の合作により,描かれたものである。 |
| 川端康成は甘縄神明神社の近くに住み、小説『山の音』を書きました。 旧川端康成邸には川端康成記念会が設立され、国宝に指定されている絵画・「紙本淡彩十便図」(池大雅)、「紙本淡彩十宜図」(与謝蕪村)、「紙本墨画凍雲篩雪図」(浦上玉堂)が所蔵されています。 |
答 ① 池大雅 ② 与謝蕪村
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (53) | 東慶寺〔 ① 〕観音菩薩半跏像は,その美しさから〔 ② 〕観音とも呼ばれる。 |
答 ① 水月 ② 楊柳

| 東慶寺の水月観音は、鎌倉地方独特の彫刻で重要文化財。 水月観音と同じような姿をしたものは水墨画に多く描かれ、岩座の水瓶に柳の枝をさしていることから楊柳観音(ようりゅうかんのん)とも呼ばれました。 |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (54) | 2019 年(令和元)6月8日に開館した〔 ① 〕 鶴岡ミュージアムは,戦後日本のモ ダニズム建築を多数手がけた建築家〔 ② 〕が設計した旧神奈川県立近代美術館鎌倉 本館に耐震・改修工事を施したものである。 |
答 ① 鎌倉文華館 ② 坂倉準三
鶴岡ミュージアム
| 2016年に一般公開を終了した「旧神奈川県立近代美術館鎌倉館」が「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」として生まれ変わり、2019年(令和元年)6月8日(土)開館。 2020年(令和2年)、旧神奈川県立近代美術館は、戦後モダニズム建築の出発点となる建物として重要文化財に指定されました。 2022年(令和4年)には、「鎌倉殿の13人」の大河ドラマ館が設置されています。 |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (55) | 鎌倉〔 ① 〕唄は,鎌倉鳶職組合によって伝承されている。毎年1月4 日,鶴岡八幡宮境内で行われる〔 ② 〕で御神木が二の鳥居から舞殿まで運ばれるときに歌われている。 |
答 ① 木遣 ② 手斧始式
| 手斧始式は、源頼朝が1191年(建久2年)の大火で焼けた鶴岡八幡宮を再建する際に、材木座海岸に着いた材木を「木遣唄」を唄いながら鶴岡八幡宮まで運び、棟梁が手斧をかけたり、墨打ちをしたことが始まりだと伝えられています。 |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (56) | 大正時代,鎌倉の銘菓である鳩サブレーが徐々に人気を博していったのは小児医学博士が幼児の離乳食に最適と推薦し,現在の〔 ① 〕小学校の地にあった鎌倉御用邸からも用命を受けたためである。また,発売当初,丸い形をしていたサブレーが鳩の形になったのは,豊島屋の初代〔 ② 〕が鶴岡八幡宮本殿の掲額の「八」の字や,境内の宮鳩からヒントを得たことによるといわれている。 |
答 ① 御成 ② 久保田久次郎

| 鶴岡八幡宮の上宮楼門に掲げられた額の「八」の字は、神聖な神の使いとされている二羽の鳩で表現されています。 この掲額をモチーフに何かできないかと考えた久保田久次郎が完成させたのが現在の「鳩サブレー」なのだとか。 |
(鳩サブレーグッズ)
| 当初は「鳩サブレー」ではなく「鳩三郎」と呼ばれていたらしい・・・ |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (57) | 毎年5月5日(端午の節句)に〔 ① 〕で行われる草鹿は,鎌倉時代の武士の射術鍛錬とされ,古式に則り,2組に分かれて鹿の形をした的に向かって矢を放ち,合計点数を競う。勝ち組の大将には神職から〔 ② 〕が授与される。 |
答 ① 鎌倉宮 ② 菖蒲

| 鎌倉宮の草鹿の起源は、1193年(建久4年)に源頼朝が催した大規模な軍事訓練である富士裾野の巻狩りといわれています。 |
| 清少納言は『枕草子』にこう書きました。 「節は五月にしく月はなし。菖蒲、蓬などのかをりあひたる、いみじうをかし」 端午の節句は菖蒲の節句とも言われます。 平安時代の端午節会では、菖蒲の長い根を贈り合う風習があったそうです。 紫式部は小少将の君から菖蒲の根を贈られています。 |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (58) | 鎌倉では,〔 ① 〕を祀る葛原岡神社の例祭を夏祭りの先駆けと呼んでいる。一方,8月16日に圓應寺で行われる〔 ② 〕で夏祭りが終わるといわれている。 |
答 ① 日野俊基 ② 閻魔縁日
| 葛原岡神社は、後醍醐天皇とともに倒幕を企て葛原ヶ岡で斬首された日野俊基を祀る神社。 俊基の命日にあたる6月3日が例大祭。 昔から「新居の閻魔さま」といえば、圓應寺の閻魔縁日といわれてきました。 |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (59) | 坂ノ下の御霊神社例祭は,祭神〔 ① 〕の命日である9月18日に行われる。境内で鎌倉神楽とも呼ばれる〔 ② 〕を奉納した後,奈良時代から伝わる伎楽面や田楽面をつけた面掛行列が行われる。 |
答
| ① 鎌倉権五郎景政(景正) ② 湯立神楽 |
 |
 |
| 鎌倉では、鶴岡八幡宮・御霊神社・八雲神社(山ノ内)で面掛行列が行われていました。 御霊神社の面掛行列は、鶴岡八幡宮の面掛行列(舞楽面の行列)に倣って、江戸時代から行われるようになったといわれ、200年以上の歴史があります。 八雲神社には7つの面が伝えられていますが、円覚寺の洪鐘祭の時に、御霊神社の面を模して作られたものです。 明治以後、鶴岡八幡宮の面掛行列はなくなり、八雲神社の面掛行列も1965年(昭和40年)に行われた円覚寺の洪鐘祭を最後に絶えて、現在では御霊神社のみで行われている奇祭となりました。 |

(東京国立博物館蔵)

| 2023年10月29日、洪鐘祭が開催されました。 |
| 令和の洪鐘祭では八雲神社の面掛行列も参加。 |
| 〔 ① 〕,〔 ② 〕ともに漢字で書きなさい。 |
| (60) | 12月16日,鶴岡八幡宮で行われる御鎮座記念祭においては,本殿での祭典後,境内の明かりがすべて消され浄闇の中,舞殿北庭に篝火が焚かれる。この明かりだけの中で,四人の巫女が「〔 ① 〕曲」に合わせて舞い,神職による「〔 ② 〕舞」が奉 納される。 |
答 ① 宮人 ② 人長

| 1191年(建久2年)3月4日、鶴岡八幡宮は未明に小町大路で起きた火事により焼失してしまいます。 源頼朝は、若宮再建とともに上宮を創建し、11月21日に遷宮が行われました(改めて石清水八幡宮の祭神を勧請しています。)。 毎年12月16日に行われている「御鎮座記念祭」(御神楽)は、遷宮の際に行われた儀式を再現したものです。 |
| 記述式その4 |
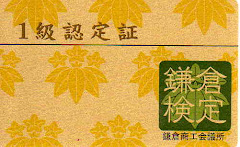
第17回1級トップ

(3級・2級・1級の問題と解説)
| ★鎌倉検定の受検お申し込みは 鎌倉商工会議所ホームページへ |
(鎌倉情報トップ)
|
|