 |
 |
 |
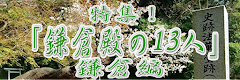 |
〜奥州藤原氏の滅亡〜
| 1189年(文治5年)7月19日、源頼朝は、奥州の藤原泰衡を征伐するため、畠山重忠を先陣に鎌倉を出発します。 |
〜戦勝祈願の社〜
(世田谷区) |
(杉並区) |
| 駒繋神社には頼朝の愛馬の伝説が残され、井草八幡宮には奥州征伐後の1193年(建久4年)、自らの手で雌雄二本の松を植えたのだと伝えられています(頼朝御手植の松)。 |
(小山) |
(宇都宮) |
| 間々田八幡宮には頼朝手植えの松(三代目)が伝えられ、二荒山神社の参拝は『吾妻鏡』に詳しく記されています。 |
| 頼朝は、朝廷に対し、源義経を匿ったことを理由に「泰衡追討の宣旨」を要求していましたが、泰衡の急襲によって義経が自刃したことにより、その大義名分が失われてしまいます。 そのため、朝廷は宣旨の発給を渋っていました。 しかし、頼朝は、大庭景義の 「軍中は将軍の令を聞き、天子の詔を聞かず・・・」 という進言を受け入れ、総勢28万4千騎の大軍で鎌倉を出発しています。 頼朝にとって、自らの命令が及ばない地は奥州のみとなっていました。 すでに義経の事は関係なく、ただ奥州を制圧することのみが目的となっていたのです。 8月11日、泰衡の異母兄国衡が守る陸奥国伊達郡阿津賀志山が頼朝軍に破られると、その報を受けた泰衡は、平泉館を焼き払い逃亡しています。 |
義経終焉の地 (高館義経堂) |
平泉政庁跡 (平泉館) |
〜泰衡からの助命嘆願〜
| 8月26日、泰衡は、頼朝に手紙を出しています。 その内容は、 「義経のことは、父秀衡が保護していたもので、 私は全くその事の始まりがわかりません。 父の死後、ご命令のとおり義経を討ちました。これは勲功というべきではないでしょうか。 そうであるのに、罪のないにも拘わらず、征伐されるというのはどういうことでしょう。 そのため、 先祖代々の在所を去って、山林をさまよい、難儀しております。 陸奥・出羽の両国は、すでに沙汰されているのですから、 泰衡についてはお許し頂き、御家人に列して頂きたいと思います。 さもなくば、死罪を減じていただき遠流にしてください。 もし御慈悲によって返答下さるのならば、比内郡辺りに置いてください。 その是非によっては帰還して参じたいと思います」 という助命嘆願でした。 頼朝は、これを受け容れず、比内郡内の探索を命じています。 |
〜奥州藤原氏の滅亡〜
| 9月3日、泰衡は、比内郡贄柵で、郎党の河田次郎に殺され、清衡以来四代にわたって栄華を極めた奥州藤原氏が滅亡しました。 |

| この頼朝の奥州での合戦は、先祖・源頼義の「前九年の役」の再現だったともいわれています。 |
奥州征伐
〜源氏の白旗〜
| 出陣前の7月8日、千葉常胤は、新調した旗二幅を献上しています。 この旗は、頼義の旗の寸法と同じで、上方に伊勢大神宮と八幡大菩薩、下方に向かい合った鳩二羽が刺繍されていたそうです。 常胤が旗の作製を命じられた理由は、頼朝が挙兵したとき、常胤が参陣してから次々と諸国の軍勢が参陣したという目出度い先例からなのだといいます(参考:鎌倉入り)。 この旗の絹を調達したのは、小山朝政でした。 これは、朝政の先祖藤原秀郷が、容易に朝敵を滅ぼしたという謂われからのことだったといいます。 献上された白旗は、三浦義澄が鶴岡八幡宮で七日間の加持祈祷を受けるよう命じられています。 |
〜鳩は八幡神の使い〜
| 「源氏の白旗」には、二羽の鳩が縫われていたようですが、鳩は八幡神の使いとされ、壇ノ浦の戦いで平家一門が入水したときには、源氏の屋形船の上に二羽の白鳩が現れたそうです(吉事の前兆〜屋島・壇ノ浦の戦い)。 |
〜釘で打ち付けられた泰衡の首〜
| 9月6日、泰衡を討った河田次郎が、泰衡の首を持参します。 頼朝は、その首を、前九年の役で、頼義が安倍貞任の首を「釘で打ち付けて晒した」のと同じように、8寸釘で泰衡の首を打ち付け、晒し首にしたといいます。 泰衡の首を持ってきた河田次郎は、 「先祖代々の恩を忘れて主人の首を刎ねるとは、八虐の罪にあたる」 として、斬罪に処せられています。 その後、泰衡の首は、父祖の眠る中尊寺金色堂に納められました。 中尊寺の大池の「中尊寺ハス」は、泰衡の首桶から発見されたハスの種が発芽したものです。 |
 |

〜奥州藤原氏の栄華〜
| 初代清衡 |
二代基衡 |
| 二代基衡の妻 |
三代秀衡 |
(多賀城市)
| 多賀城は、源頼義・義家が軍事拠点とした地。 頼朝も奥州征伐の際には、それに倣って立ち寄っている。 |
(宇都宮市:三峰山神社)
| 三峰山神社の墓塔は、奥州征伐後に源頼朝が生贄として二荒山神社に奉献した樋爪俊衡と弟の季衡、あるいは、季衡とその子経衡のものなのだという。 俊衡は奥州藤原氏初代清衡の四男清綱の子。 |
(港区)
| かつては江戸城の桜田門外(霞が関)にあったのだという桜田神社。 奥州征伐の祈願成就の礼として頼朝は神田を寄進。 神田の畔に植えられた桜が「桜田」の由来なのだとか・・・ |
(新宿区)
| 神楽坂若宮八幡神社は、奥州を平定した頼朝が鶴岡八幡宮の若宮を勧請したのが始まりと伝えられています。 |
(埼玉県ときがわ町)
| 慈光寺は、頼朝が伊豆の流人だった頃から信仰していた観音霊場。 奥州征伐の際には愛染明王像を贈り、戦勝を祈願させています。 奥州平定後には愛染明王の御供米を贈り、鎮守社の萩日吉山王宮には北条政子の名で田畑が寄進されたのだといいます。 |
|
|

|
|
(鎌倉情報トップ)