 |
浄 妙 寺
=鎌足の鎌槍伝説=
|
|
| 浄妙寺(臨済宗建長寺派)は、1188年(文治4年)、源頼朝の重臣足利義兼が父義康の菩提を弔うために創建した真言宗の極楽寺を前身としている。 開山には鶴岡八幡宮の供僧だった退耕行勇が迎えられた。 行勇は、源頼朝や北条政子も帰依した高僧。 義兼の子義氏のときに住持となった月峯了然によって臨済宗に改められ、足利尊氏が父貞氏の法号「浄妙寺殿貞山道観」にちなんで寺名を浄妙寺と改めたのだと伝えられている。 |
| ※ | 寺名を改めたのも臨済宗に改宗した頃(正嘉年間(1257〜59年)という説もある。 |
(聖観世音) (釈迦如来) |
| 開山 | 退耕行勇 |
| 開基 | 足利義兼 |
| 本尊 | 釈迦如来 |
| 開山の退耕行勇は、重源・栄西の跡を継いで東大寺の第三代大勧進職に任じられている。 |
足利義兼像
| 開基の足利義兼は、1195年(建久6年)、東大寺の大仏殿落慶供養に参列する源頼朝に従い上洛。 東大寺で出家した。 頼朝による源氏粛正を避けるためだったという。 出家後は、下野国足利荘の樺崎寺に隠棲。 樺崎寺は廃寺となったが、安置されていた大日如来は運慶仏として伝えられている。 |

| 足利貞氏は足利宗家七代当主。 本堂背後の墓地にある宝篋印塔は貞氏の墓とされている。 |
| 源頼朝の側近足利義兼〜鎌倉:浄妙寺開基〜okadoのブログ |
| 現在の浄妙寺は、総門・本堂・庫裡というたたずまいだが、かつては足利氏の保護下で鎌倉五山に列せられるほど栄えた。 浄妙寺に伝わる古絵図には、外門・総門・山門・仏殿・法堂・方丈・禅堂・経堂などの伽藍や23に及ぶ塔頭が描かれているらしい。 しかし、室町時代には、寺域に隣接して鎌倉公方屋敷があったことから、寺も度重なる戦乱による被害を免れることはできず、1438年(永享10年)に起こった「永享の乱」以後の詳しい事は伝えられていない。 |
 |
 (本寂堂) |
| 喜泉庵は、1991年(平成3年)に復興された茶室。 |
| 藤原鎌足伝説 |
 |
| 「鎌倉」という地名の由来については、いつくかの説があるようだが、浄妙寺の鎌足稲荷神社の伝説もその一つ。 鎌足桜は、鎌足の持っていた杖が根づいたという伝説の桜。 |
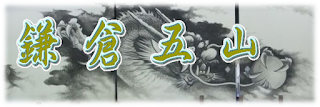
| 五山の制度は、禅寺の格式を表すもの。 室町幕府三代将軍足利義満の時代に、京都の南禅寺が五山之上に置かれ、鎌倉五山と京都五山が決められた。 |
一位 |
二位 |
三位 |
四位 |

| 浄妙寺で最期を遂げた足利直義 (尊氏の弟) |
 (熊野神社) |
 (足利直義の墓) |
| 浄妙寺に隣接する熊野神社の上り口辺りには、足利直義の屋敷があったとされ、直義の菩提所として建てられた大休寺があったのだという。 直義は足利尊氏の弟。 1352年(文和元年・正平7年)に浄妙寺境内の延福寺に幽閉され、2月26日に急死した。 |
参考

| 浄妙寺の境内にある古い洋館を利用した洋食レストラン。 |
| 鎌足稲荷参道の庚申塚 |



浄妙寺
| 鎌倉市浄明寺3−8−31 0467(22)2818 鎌倉駅から金沢八景・大刀洗行・ハイランド循環バス 「浄明寺」下車徒歩1分 |
鎌倉の臨済宗の寺
鎌倉:寺社・史跡めぐり
金沢街道沿い
| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |
(鎌倉情報トップ)
 |
 |
 |
 |
 |
|
|