京都:五条大橋
牛若丸と弁慶の伝説
|
|

| 五条大橋は、五条通の鴨川に架けられた橋。 平安時代末に牛若丸(源義経)と弁慶が出会ったという伝説で知られる橋。 ただ・・・ 現在の「五条通」は当時の「六条坊門小路」に当たり、平安時代の五条通(五条大路)は、清水寺から清水坂を下り鴨川を渡って松原通へとつながる道だった。 したがって、牛若丸と弁慶が出会ったのは現在の「松原橋」ということになる。 |

| 松原通は、清水寺の門前から東大路通までの道で、清水道とも呼ばれている。 鴨川に架かる松原橋は、かつては五条橋と呼ばれていたが、豊臣秀吉が方広寺の大仏参詣の便をよくするため五条橋を南へ移したのだという。 |
| 五条大橋 |
| 京阪電車「清水五条」下車 西へ100メートル |
〜伝説!牛若丸と弁慶の出会い〜
| 乱暴者の弁慶は、千本の太刀を奪おうという悲願を立て、道行く人を襲っては太刀を奪い取り999本までになった。 そして、あと一本というところで、五条大橋を横笛「薄墨」を吹きながら通る牛若丸と出会う。 弁慶は牛若丸に襲いかかるが、牛若丸は欄干を飛び交い、最後は返り討ちに遭ってしまう。 降参した弁慶は、その後牛若丸の家来になったのだという。 |

牛若丸と弁慶の像
| 五条大橋の西詰には、京人形風に作られた「牛若丸と弁慶の石像」が建てられている。 |
唱歌:牛若丸
| 京の五条の橋の上 大のおとこの弁慶は 長い薙刀ふりあげて 牛若めがけて切りかかる 牛若丸は飛び退いて 持った扇を投げつけて 来い来い来いと欄干の 上へあがって手を叩く 前やうしろや右左 ここと思えばまたあちら 燕のような早業に 鬼の弁慶あやまった |
| 祇園祭の後祭(山鉾巡行)で巡行する橋弁慶山は、五条大橋で牛若丸と弁慶が争う場面を表したもの。 |
〜日の丸〜
| 牛若丸が弁慶に投げつけた扇には日の丸が描かれていたのだとか・・・ 牛若丸の先祖・源頼義は後冷泉天皇から御旗(日の丸の旗)を賜った。 その旗は、甲斐武田家に伝えられ、現在は山梨県甲州市の雲峰寺が所蔵している。 義経も源平合戦で日の丸を掲げたのだという。 |
〜義経と弁慶の決戦の場所〜
| 参考までに・・・ 『義経記』では、牛若丸と弁慶が出会ったのは五條天神社。 最終決闘の場所も五条大橋ではなく、清水寺での出来事だったのだという。 |

| 清水の舞台で牛若丸に負けた弁慶は、牛若丸に臣従したのだという。 |
〜義経の笛〜
| 牛若丸が弁慶と出会った時に吹いていた横笛は、新羅三郎義光伝来の笛で、源義朝→常盤御前と伝えられたのだといわれる。 義経は、この笛を駿河国の久能寺に奉納したのだという。 |
(静岡市)
| 久能寺は、戦国時代に武田信玄が久能城を築いたことで移転し、武田氏滅亡後、久能城の跡地には徳川家康を祀る東照宮が創建された。 移転した久能寺は鉄舟寺として再興され、義経の「薄墨の笛」とされる横笛が伝えられている。 |
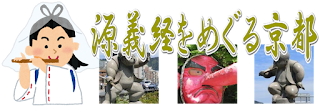
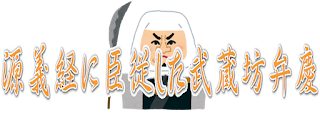

扇塚
| 五条大橋の西北詰は、1284年(弘安7年)に建てられた御影堂(新善光寺)があった場所。 かつて、ここでは「御影堂扇」が作られていた。 「御影堂扇」は、平敦盛の室(蓮華院尼)が考案したものと伝えられ、最上の扇とされていたという。 |
| 平安神宮の神苑にある臥龍橋は、天正年間に豊臣秀吉が架けた三条大橋と五条大橋の橋脚が使用されている。 |





 |
 |
 |
 |
|
|