 |
 |
称 名 寺
(横浜市金沢区)
|
|
| 金沢北条氏の祖北条実時が建てた持仏堂が称名寺のはじまりと推定されているが、創建の時期は明らかではない。 金沢北条氏の菩提寺であるとともに、学問寺としても大いに栄えた。 三代執権北条泰時によって朝夷奈切通が開かれると、泰時の弟実泰が鎌倉に接した六浦の地頭となり、その子実時は、鎌倉から六浦荘金沢に館を移した。 文書・書籍などの書物を火災等の災害から守るための書庫「金沢文庫」を建てるためともいわれている。 実時の子顕時の時代には、弥勒堂、護摩堂、三重塔が建立され、顕時の子貞顕の時代には七堂伽藍を備えた壮麗な寺となった。 しかし、1333年(元弘3年)、新田義貞の鎌倉攻めによって鎌倉幕府が滅びると衰退した(参考:鎌倉幕府の滅亡)。 塔頭光明院の「大威徳明王像」は、運慶の真作と判明している。 |
| 開山 | 審海 |
| 開基 | 北条実時 |
| 本尊 | 弥勒菩薩 |
北条実時像
| 1258年(正嘉2年)5月、北条実時は紫式部の『源氏物語』を写した「河内本」の原本を借りて書写させている。 それが尾張徳川家に伝えられた「尾州家本源氏物語」なのだとか。 |
〜金沢郷〜
| 武蔵国久良岐郡六浦荘金沢郷は畠山重忠の所領だったが、1205年(元久2年)の畠山重忠の乱で重忠が謀殺されると北条義時の所領となり、義時の子実泰に与えられたのだという。 |
(赤門) |
(清涼寺式釈迦如来) |
(阿字ヶ池) |
 |

| 塔頭光明院の大威徳明王は運慶の真作。 発願者は、源頼家と源実朝の養育係を務めた大弐局。 京都の東寺の講堂に安置されている像の模刻といわれている。 |
 |
 |
 |
| 金沢北条氏三代目の貞顕は、京都に常在光院を築き、優美な庭園を造営したのだという。 その場所は定かではないが、浄土宗の総本山知恩院の方丈辺りではないかという説がある。 |
| 金沢文庫は、北条実時によって創設された武家の書庫。 |
☆伝説!謡曲「六浦」☆
| 京都の僧が称名寺を訪れて、山々の楓は紅葉の盛りなのに本堂前の楓が一葉も紅葉していないのを不審に思うと「楓の精」が現れて・・・ 昔鎌倉の中納言為相卿が、山々の紅葉はまだなのに、この楓だけ紅葉しているので 「いかにしてこ一本に時雨(しぐれ)けん山に先立つ庭のもみじ葉」 と詠むと、 楓は非常に光栄に思い 「功なり名とげて身退くは天の道」 の故句に倣い、 「その後は紅葉せず常緑樹になったこと。草木にはみな心があること」 を語り、僧に仏法を説くよう頼み、木の間の月に紛れて消え去ったのだという。 |
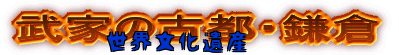

称名寺
| 横浜市金沢区金沢町212−1 京浜急行金沢文庫駅下車徒歩15分。 |

六浦史跡巡りMAP
| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|