 |
 |
法華堂跡
|
|
| 「法華堂跡」は、大倉幕府跡の裏山にある源頼朝墓を中心とする史跡。 法華堂は、1189年(文治5年)、源頼朝が奥州征伐の祈願所として、伊豆山権現の專光房良遷に命じて建立した持仏堂が始まり。 本尊は聖観音像。 1191年(建久2年)には、文覚に命じて京都で描かせた阿弥陀三尊像が掛けられた。 持仏堂は、頼朝の死後「法華堂」と呼ばれるようになり、現在、源頼朝墓が建てられている場所が法華堂の跡だといわれている。 |
| 持仏堂の本尊は聖観音像 |
| 『吾妻鏡』によると、頼朝の持仏堂の本尊は、京都の清水寺から下されたという二寸銀の聖観音像。 1180年(治承4年)の源氏再興の挙兵の際に髷の中に納めていたものなのだという(参考:しとどの窟)。 |
| 源氏重代の太刀 |
| 持仏堂(法華堂)には、1159年(平治元年)の平治の乱で、初陣の頼朝が帯びていたという源氏重代の太刀「髭切」(ひげきり)も納められていたのだという。 現在、京都の北野天満宮所蔵の髭切がそれではないかとも(参考:一条戻橋の伝説))。 |

| 国指定史跡法華堂跡 |
| 鎌倉幕府を開いた源頼朝の墓と、二代執権・北条義時の墓は、「史跡法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)」として国指定史跡に指定されている。 |
| 源頼朝墓の下にあるのは、頼朝を祀る白旗神社。 明治の神仏分離までは法華堂と呼ばれていた。 |
| 源頼朝墓の東の山腹にある平場は、2005年(平成17年)に行われた発掘調査の結果、北条義時の法華堂跡ではないかと考えられている。 平場の北面には、1247年(宝治元年)の宝治合戦で頼朝の法華堂で自刃した三浦泰村一族の墓がある。 |
| 北条義時法華堂跡の上方のやぐら内には、頼朝の片腕として活躍した大江広元、その子毛利季光、頼朝の子ともいわれる島津忠久の墓が建てられている。 |
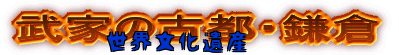
| 源頼朝の御所跡 |
| 鎌倉幕府のうち、頼朝・頼家・実朝の源氏3代と北条政子が政務を執った場所を「大倉幕府」と呼んでいる。 現在の清泉小学校の周辺が大倉幕府の跡で、源頼朝墓の下一帯がいわゆる「鎌倉幕府」であった。 政子亡き後、幕府は移転・・・ 三代執権北条泰時は、1225年(嘉禄元年)、大倉幕府を宇津宮辻子に移したので「宇津宮辻子幕府」と呼ばれ、1236年(嘉禎2年)には若宮大路に移したため「若宮大路幕府」と呼ばれている。 |
| 源頼朝の遺髪 |
| 横浜の東戸塚にある平戸白旗神社には、法華堂に納められていた源頼朝の遺髪のうち三筋が送られたのだという。 |

(源頼朝ゆかりの寺社・史跡など)

(誕生から最期までの歴史)
法華堂跡
| 鎌倉市西御門2丁目 鎌倉駅東口より徒歩20分 |
鶴岡八幡宮周辺・西御門・二階堂
| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |
(鎌倉情報トップ)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|