 |
 |

|
|
| 「節分」とは、季節の分かれ目(節目)のことで、本来、立春・立夏・立秋・立冬の前日のことですが、今日では、立春の前日を主に「節分の日」と呼んでいます。 |
| 立春 | ⇒ | 2月4日ころ |
| 立夏 | ⇒ | 5月6日ころ |
| 立秋 | ⇒ | 8月7日ころ |
| 立冬 | ⇒ | 11月7日ころ |
| 2026年の節分は 2月3日(火) |
| 節分は、節目の邪気(鬼)払いを行う日。 大寒から立春となる節目に、鬼に豆をぶつけ、邪気を追い払い、無病息災を願うという意味があります。 詳しい情報は写真をクリック。 |
13:00〜 |
(鶴岡八幡宮) |
| 鶴岡八幡宮では、弓の弦を鳴らして鬼を追い払う「鳴弦の儀」が行われます。 |
11:00〜 |
15:00〜 |
| 建長寺では、豆まきの前に「節分会大祈祷」と「かっぽれの奉納」があります。 鎌倉宮では、鐘や太鼓で鬼を追い払う「鬼やらい」の神事が行われます。 |
| 鬼の角とパンツ |

| 鬼が出入りする方角を鬼門と呼びます。 鬼門は、丑寅(うしとら)の方角(北東)。 ということで・・・ 鬼の角は牛(丑)を、パンツは虎(寅)を表しているのだとか。 |
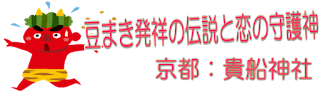
11:30〜 |
 10:00〜 (1月31日) |
| 長谷寺では、豪華ゲストを迎えての豆撒きが行われます。 御霊神社の節分祭は1月31日(土)の予定。 12歳になった少年・少女による豆撒きです。 |
13:00〜 |
 1回目:13:00〜 2回目:14:30〜 |
| 龍口寺では、節分の供養に先立って水行が行われます。 |
10:00〜 |
13:00〜 (2月1日) |
| 江島神社の節分祭は舞台を設営しての豆まきや景品交換はありません。 大船観音寺の節分祭は、節分前の2月1日、厄除祈祷に参列するとゲストと一緒に豆まきができます(要申込)。 |
| 「節分祭」は、邪気(鬼)を追い払うための行事として古くより行われています。 「節分」には、炒った大豆を撒きます。 鬼に豆をぶつけ、邪気を追い払い、無病息災を願うという意味があります。 また、撒いた豆を自分の歳の数だけ食べると体が丈夫になるといわれています。 豆を撒く際には、「鬼は外、福は内」と声を掛けるのが一般的ですが、鬼を祭神としている神社や鬼の付く姓の多いところでは、「鬼は内」と声を掛けるようです。 |
| 節分に飾る「柊鰯」 |
| 柊鰯(ひいらぎいわし)は、焼いた鰯(いわし)の頭を柊(ひいらぎ)の葉に刺し、玄関に飾る魔除けの風習。 鬼を柊のトゲと鰯の臭いで追い払うのだとか。 |
| 豆まきの由来は大晦日の追儺 |
| 節分の豆まきは、大晦日に宮中で行われていた悪鬼を追い払う「追儺」(ついな)という行事に由来。 追儺は「おにやらい」「なやらい」とも呼ばれていました。 紫式部の『源氏物語』にも描かれています。 |
| 方違えと豆まき |
| 『枕草子』には節分に方違えが行われていたことが記されている。 清少納言は「すさまじきもの」としているが、それが「豆まき」へと変化していったらしい。 |
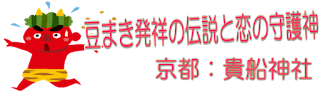


(鎌倉情報トップ)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|