 |
| 溺れかけた大串重親を岸に投げ上げた畠山重忠 |
|
|
| 1184年(寿永2年)1月20日、木曽義仲追討のため、源義経に従って宇治を攻めた畠山重忠。 『平家物語』によると・・・ 宇治川は、白波がたち、瀬枕では滝のような音を立てて、激しく流れていた。 霧が深く立ち込めた早朝、義経は、一口(いもあらい:芋洗)へ向かうか、河内路に迂回するか、それとも水が引くのを待つか、思案していた。 すると重忠が、 「この川は琵琶湖から流れ出ているので、水が引くことはありません。 去る治承の合戦(宇治平等院の戦い)で、17歳の足利忠綱はこの川を渡りました。 先ずは、重忠が瀬踏みしてみます」 と言って、五百騎余りを並べて水の深さを調べたのだという。 その間、平等院方面から駆けてきた梶原景季と佐々木高綱が先陣を争って宇治川へ入っていく。 この先陣争いでは、高綱が勝ち、 「宇多天皇より九代の後胤、近江国の住人、佐々木三郎秀義が四男、佐々木四郎高綱、宇治川の先陣!」 と名乗っている。 その後、重忠も五百騎余りを川にうち入れて渡っていった。 しかし、向こう岸から山田次郎が放った矢が重忠の馬の額を深く突き刺した。 弓を杖の代わりにして馬から降りた重忠は、兜の手先まで押し寄せてくる波をもろともせず、川底に潜り、向こう岸までたどり着いた。 そして、岸に上がろうとしたとき、背中を力強く掴む者がいた。 重忠が「誰だ」と問うと「重親です」と答える。 さらに「大串か」と問うと「そうでございます」と答えた。 大串重親は、重忠の烏帽子子。 「あまりに水の流れが速く、馬を川中で押し流されてしまいました。 力が及ばず、重忠様につかまっておりました」 と語る大串に重忠は、 「お前たちのような者は、いつまでも重忠に助けられるのだな」 と言って、大串を掴んで岸の上に投げ上げた。 放り投げられた大串は・・・ 立ち上がり、太刀を抜いて額にあて、大声を上げて、 「武蔵国の住人、大串次郎重親、宇治川の先陣!」 と名乗ったのだという。 敵も味方もこれを聞いて、いっせいにどっと笑ったのだとか・・・ |
| 大串重親(おおぐししげちか)は、武蔵国大串郷(現在の比企郡吉見町大串)を本拠とした武将。 1189年(文治5年)の奥州合戦では、阿津賀志山の戦いで藤原国衡を討ち取ることに貢献。 1205年(元久2年)の畠山重忠の乱では、北条義時の軍にいたが、弓を収めて撤退したのだという。 |

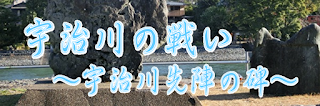

2022年のNHK大河ドラマは・・・
北条義時!




(鎌倉情報トップ)
 |
 |
 |
 |
 |
|
|