|
|
| 「白馬節会」(あおうまのせちえ)は、正月七日に行われていた天皇が白馬(あおうま・青馬)を観覧する儀式。 中国で発生した陰陽五行説の「春に陽のものを見ると邪気が避けられる」という考えに基づくもの。 陰陽五行説では「馬」は陽、春の色は「青」。 この二つ(馬と青)が結びついたのが「白馬節会」。 もともとは青毛の馬を用いていたため「あおうまのせちえ」と読ませていますが・・・ 平安中期の村上天皇の時代には「白馬」と書かれはじめたようです。 それまでの日本は中国の影響を受けた文化でした。 中国では青が高貴の色とされていたため、日本もこれに倣っていましたが、平安中期以降は独自の文化(国風文化)が発展。 次第に白が上位に置かれるようになり、白馬が用いられるようになったようです。 ただ、白馬を用いるようになってからも「あおうま」の読みは残されました。 |
| ※ | 白馬の画像は、以仁王を祀る高倉神社の神馬。 |
| 白馬節会では、天皇が豊楽殿に出御し、庭に引き出される白馬を御覧になり、群臣と宴が催されていました。 紫式部の『源氏物語』には、光源氏が私邸の二条邸で白馬節会を催したことが描かれていますが、貴族の私邸で催されていたかどうかは不明です。 後に紫宸殿で行われるようになりましたが明治維新に廃絶。 京都の上賀茂神社では「白馬奏覧神事」(はくばそうらんしんじ)、大阪の住吉大社では「白馬神事」(あおうましんじ)として宮中の「白馬節会」を伝承しています。 茨城県の鹿島神宮の「白馬祭」(おうめさい)は、鎌倉幕府四代将軍の藤原頼経が宮中よりもたらした祭事と伝えられています。 |
正月七日、もう一つの行事
正月15日の邪気払い
無病息災・旅行安全!
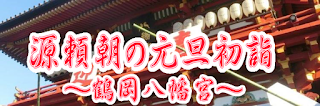





|
|