|
|
| 1月7日は七日正月。 古代中国では、 「正月1日は鶏を占い、2日には狗を占い、3日には羊を占い、4日には猪を占い、5日には牛を占い、6日には馬を占い、7日には人を占い、8日には穀を占う」 という風習がありました。 そして、7日の「人日の節句」には、一年の無病息災を願って「七種菜羹」(ななしゅさいのかん)を食する習慣がありました。 七種菜羹は、七種類の野菜(七草)を入れた羹(あつもの・吸い物)。 そのため「人日の節句」は「七草の節句」とも呼ばれています。 |
| 日本には・・・ 古代から正月最初の子の日に雪の間から芽を出した草を摘む「若菜摘み」という習慣がありました。 後に六日年越の行事となります。 六日年越は七日正月の前日(6日)。 6日に摘まれた若菜は、健康や長寿を祈る贈り物として使われていたのだといいます。 この風習が中国から伝えられた七草の吸い物「七種菜羹」(七草羹)と融合して「七草粥」となったのだとか。 清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』にも「若菜摘み」の話が登場しますが、平安時代はまだ中国と同じく七草羹。 粥として食されるようになったのは室町時代からのようです。 平安時代の七草が何の草だったのかはわかりませんが・・・ 室町時代には 「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」 に定着していたようです。 |
(伊勢原市 日向薬師)
| 源頼朝や北条政子が信仰した日向薬師では、1月8日の初薬師に餅入りの七草粥(薬師粥)が振舞われます。 |
| 小正月の七種粥・小豆粥 |
| 参考までに・・・ 平安時代には米・あわ・小豆・きび・ひえ・ごま・みのなどの穀物を中心とした「七種粥」があったそうで、正月15日(小正月)に食されていたようです。 現代でも正月15日に一年の健康を願って「小豆粥」を食べる風習が全国各地に伝承されていますが、「七草羹」が「七草粥」になったのも「七種粥」の影響からかもしれません。 |
正月七日、もう一つの行事
| 白馬節会は宮中で行われていた邪気払いの行事。 それを伝承する上賀茂神社の「白馬奏覧神事」では七草粥が振舞われます。 |
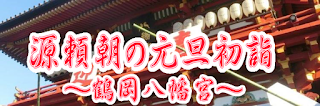





|
|