|
|
| 1月15日は小正月。 平安時代、一年中の邪気を払うため、小正月の朝には「十五日粥」(じゅうごにちがゆ)を食べる風習がありました。 十五日粥には、米・粟・黍・稗子・篁子・胡麻・小豆の七種類の穀物が使われたので「七種粥」(ななくさがゆ)とも呼ばれていました。 また、15日は満月(望月)であることから、「望粥」(もちがゆ)とも。 |
| 七種粥から小豆粥へ |
| 古代中国では、小豆の赤色には魔除けの力がある信じられ、「冬至に小豆の粥を食べて邪気を祓い冬に備える」という風習があったようです。 正月15日にも豆粥が作られていますが、中国の伝説によると、蚕の精のお告げによるものなのだとか。 この「小豆粥」が奈良時代に日本へ伝えられて「七種粥」となり、天平年間には東大寺の大仏殿に供えられた記録が残されているのだといいます。 天皇の即位後に行われる大嘗会でも、穀物への感謝の意味で食されていたそうです。 小豆粥が七種粥となった理由はわかりませんが、中国から伝えられた七草の吸い物「七種菜羹」(ななしゅさいのかん)の影響もあるのだとか。 いずれにしても、正月15日に食べる粥は、邪気を祓う赤色をしているということが重要です。 七種粥にしても、小豆が入っているので赤色をしていたはずです。 しかし、七種粥は次第に略式化され、中国から伝えられた小豆粥へと変化していきます。 平安中期に成立した紀貫之の『土佐日記』には「正月十五日なのに船中なので小豆粥が食せない」と記されています。 |
| 粥 杖 |
| 「粥杖」(かゆづえ)は、粥を炊いた薪の燃え残り。 粥杖で女性の尻をたたくと子宝に恵まれるとか、男の尻をたたけばその人の子を宿すなどといわれていました。 民間で流行った風習ですが、宮廷でも流行し、清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』にも登場しています。 |
| 餅入りの小豆粥 |
餅入りの小豆粥
(北海道農政事務所HPより)
| 京都の下鴨神社や妙心寺の塔頭東林院などでは、「餅入りの小豆粥」が振舞われますが・・・ 正月15日に食べる粥は「望粥」(もちがゆ)とも呼ばれたことから、「望」が「餅」に読み替えられて「餅入りの小豆粥」が生まれたのだとか。 |
| 七種粥と七草粥 |
| 「七種粥」と「七草粥」は、どちらも「ななくさがゆ」と読ませますが・・・ 「七種粥」は穀物を中心とした粥、「七草粥」は春の七草を使った粥。 「七草粥」は、1月7日に無病息災を祈って食べられますが、古代中国から伝えられた「七種菜羹」と日本の「若菜摘み」の風習が融合して生まれた食べ物らしい。 |
1月7日には白馬節会も
(鎌倉 鶴岡八幡宮)
| 左義長神事は、暖かい春の到来と今年の豊かな収穫を祈る火祭り。 火に身体をあてると若返るとか、火で餅や団子・繭玉を焼いて食べると病気にかからず達者で暮らせるなどと伝えられています。 |
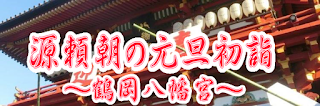





|
|